もしも懲戒解雇されて最悪の場合はどうなる?
懲戒解雇は、その後の人生やキャリアに大きな影響を与える可能性があり、実際に困難な状況に陥るケース可能性があります。自業自得とはいえ、社会復帰が難しくなる可能性があります。
以下の小説はフィクションです。
情報漏洩による懲戒解雇後の転落
前提条件:
- 人物: 42歳男性
- 状況: 情報漏洩で懲戒解雇。退職金なし、失業保険給付なし。
- 家族: 妻と子(1人)がいたが、離婚し妻が子を連れて実家へ。養育費の支払い義務あり。
- 資産: 貯金100万円
- 負債: 持ち家(一軒家)の住宅ローン残高1000万円
- キャリア: 懲戒解雇によりキャリア断絶、再就職は絶望的。
- 運: 常に最悪の方向へ進む。
注記: これはあくまでフィクションであり、最悪の事態を想定したシミュレーションです。現実には、公的な支援制度(生活困窮者自立支援制度など)、NPO法人による支援、家族や友人からのサポートなど、再起のための様々な道が存在します。しかし、このシミュレーションでは、それらの可能性が全て閉ざされた場合の転落過程を描いています。
Xデー
午前9時15分
いつものように、少しだけ濁ったオフィスビルの窓から差し込む朝日を浴びながら、佐藤健一(42歳)はキーボードを叩いていた。中堅のシステム開発会社に勤めて15年。役職こそ課長代理止まりだが、部署内では頼られる存在だった。特に、最近こっそり導入した海外製のプロジェクト管理ツールは、チーム内の情報共有を劇的に改善した、と自負していた。もちろん、会社の正式な許可は得ていない。いわゆる「シャドーIT」だ。申請が面倒だったし、どうせ「セキュリティが」と却下されるのが目に見えていたから。「効率が上がるんだから、結果的に会社のためだろ」そう自分に言い聞かせ、便利さを享受していた。
「佐藤さん、昨日のバグ修正、助かりました!」
隣の席の後輩、田中が明るい声をかけてくる。
「おう、まあな。あのツールのおかげで、どこで詰まってるかすぐ分かったからな」
健一は少し得意げに答えた。田中もそのツールの便利さは知っているが、健一ほどヘビーユーザーではなかった。
午前中は、クライアントとの定例ミーティング、溜まっていたコードレビュー、そしていくつかの細かな修正作業で、あっという間に過ぎていった。昼休みは、愛妻弁当の唐揚げを頬張りながら、スマホで住宅ローンの繰り上げ返済シミュレーションを眺める。あと1000万円。小学校に上がったばかりの一人息子、翔太の将来のためにも、少しでも早く完済したい。平凡だが、確かな幸せがそこにはあった。
午後1時30分
昼休憩が終わり、午後の業務が始まったばかりの、少し気だるい時間帯。健一はコーヒーを淹れ、自分のデスクに戻った。さあ、午後は新規案件の仕様検討に集中しよう、と思った矢先だった。
ピロン、とPCのチャット通知が鳴った。発信者は人事部長の鈴木。CCには直属の上司である開発部長の山田も入っている。
『佐藤課長代理、至急、第3会議室までお越しください。山田部長も同席されます。』
短い、事務的な文面。だが、普段のやり取りとは違う、妙な硬さを感じた。人事部長から直接、しかも上司同席での呼び出しなど、記憶にない。「至急」という言葉も引っかかる。
(何か、俺、やらかしたか…? いや、最近大きなミスはなかったはずだが…)
一瞬、例のツールのことが頭をよぎったが、すぐに打ち消した。「まさか、バレるわけない」。軽い懸念を抱きつつも、まだ事態の深刻さには気づいていなかった。
「ちょっと呼ばれたんで、行ってきます」
田中に声をかけ、健一は席を立った。第3会議室は、役員会議などでも使われる、少し離れた場所にある部屋だった。
午後1時45分 第3会議室
重いドアを開けると、そこには予想通り、人事部長の鈴木と、開発部長の山田が硬い表情で座っていた。部屋の中央に置かれた長テーブルには、数枚の書類が置かれている。健一が促されるまま向かいの席に座ると、部屋には息苦しいほどの沈黙が流れた。いつもは冗談も飛ばす山田部長が、目を合わせようとしない。
先に口を開いたのは、人事部長だった。
「佐藤君、単刀直入に聞きます。あなたが個人的に契約し、業務で使用している『ProjectFlow Pro』というツールについて、説明してもらえますか?」
そのツール名は、健一が「便利だ」と使っていた、まさにあの海外製プロジェクト管理ツールだった。血の気が引くのを感じた。なぜ、それがバレた?
「え…あ、はい。チーム内のタスク管理を効率化するために、私が個人的に…」
しどろもどろになりながら答える。
「そのツールが、外部からの不正アクセスの起点となり、現在開発中の次期主力製品に関する機密情報を含む、複数のプロジェクトデータが外部に流出した可能性が極めて高い、ということが、昨夜、セキュリティ部門の調査で判明しました」
鈴木部長は、淡々と、しかし有無を言わせぬ口調で続けた。テーブルの上の書類は、アクセスログや調査報告書のようだった。
「なっ…! そん、な…! 私が使っていたツールから…?」
健一は言葉を失った。良かれと思ってやったことだ。情報漏洩なんて、考えもしなかった。
「あなたの個人アカウントのパスワードが非常に脆弱であったこと、そして、そのツール自体のセキュリティホールが利用された形跡があります。会社が許可していないツールを業務利用し、結果として会社に計り知れない損害を与えた。これは、就業規則の重大な違反行為に該当します」
隣で黙っていた山田部長が、苦々しい表情で口を開いた。
「佐藤…お前、なんで相談してくれなかったんだ…。こんなことになるなんて…」
健一の頭は真っ白になった。不正アクセス? 情報漏洩? 会社に損害? まるで現実感がない。悪い夢を見ているかのようだ。
鈴木部長は、一枚の書類を健一の前に滑らせた。そこには、はっきりとこう書かれていた。
『懲戒解雇通知書』
「…懲戒、解雇…?」
声が震えた。
「はい。今回の事態を極めて重く受け止め、取締役会で決定しました。本日付で、佐藤健一さんを懲戒解雇とします」
鈴木部長は続けた。
「なお、懲戒解雇の場合、当社の規定により、退職金の支給はありません。また、失業保険の給付に関しても、自己都合退職よりも厳しい条件、場合によっては給付制限や不支給となる可能性があることを申し添えておきます」
退職金なし。失業保険も…?
頭の中で、住宅ローンの残高、翔太の学費、妻の顔がぐるぐると回り始めた。目の前が暗くなるような感覚。
「そんな…待ってください! 悪気があったわけでは…! 少しでも仕事を効率的に進めようと…!」
必死に訴えようとしたが、鈴木部長は冷ややかに首を横に振った。
「あなたの動機がどうであれ、結果が全てです。会社の信用を著しく毀損し、多大な損害を与えた事実は変わりません」
もう、何も言葉が出てこなかった。全身から力が抜け、椅子に座っているのがやっとだった。15年間勤めてきた会社、築き上げてきたキャリア、守りたかった家族との生活…その全てが、今、この瞬間、音を立てて崩れ落ちていく。
「…今後の手続きですが、この後、あなたのデスクにある私物をまとめていただきます。会社のPC、貸与品は全て返却してください。セキュリティ担当者が同行します」
事務的な説明が、遠い世界の出来事のように聞こえた。
どれくらいの時間が経ったのか。健一は、ふらつく足取りで、人事部長と山田部長に一礼する気力もなく、会議室のドアに向かった。ドアノブに手をかけた瞬間、ガラスに映った自分の顔は、見たこともないほど青ざめ、憔悴しきっていた。
会議室の外には、人事部の社員と、見慣れないセキュリティ担当者らしき男性が、硬い表情で立っていた。これから始まる「後処理」が、健一を現実へと引き戻そうとしていた。しかし、彼の心はまだ、突然突きつけられた絶望の淵で、呆然と立ち尽くすばかりだった。
Xデーの午後
午後2時15分
重い足取りで第3会議室のドアを開け、廊下に出た瞬間、健一は全身に突き刺さるような視線を感じた。人事部の社員とセキュリティ担当者に両脇を固められるようにして歩く姿は、どう見ても尋常ではない。オフィスフロアに戻るまでの短い廊下でさえ、すれ違う社員たちは一様に驚いた顔をし、健一の姿を目で追った。彼らの視線には、戸惑いと、何かが起こったことを察したような好奇の色が混じっていた。
自分の部署があるフロアに足を踏み入れると、空気はさらに重くなった。さっきまで普通に会話を交わしていた同僚たちが、一斉にこちらを向く。そして、次の瞬間には、バツが悪そうに視線を逸らしたり、あるいは、あからさまな好奇心で健一と付き添いの二人を観察したりしていた。噂は、すでに光の速さで伝播しているのだろう。
「佐藤さんが人事とセキュリティに連れられて…」
「何か重大な問題を起こしたらしい…」
そんな囁き声が、幻聴のように健一の耳にまとわりつく。
特に、先ほどまで隣で普通に仕事をしていた後輩、田中の視線が痛かった。驚きと、信じられないという表情。健一は、彼と目を合わせることができなかった。15年間、真面目に、時には泥臭く働いてきた自負があった。それが、こんな形で終わるのか。羞恥と屈辱で、顔から火が出るようだった。
「佐藤さん、こちらへ」
人事部の社員が、健一のデスクへと促す。セキュリティ担当者は、無言でその後ろに立つ。まるで、逃亡を防ぐ監視役のようだ。
「あなたの私物はこちらの段ボールに入れてください。会社の資産、書類、データ類は一切持ち出さないように」
事務的な口調で指示される。
健一は、ロボットのように動き始めた。デスクの上には、家族の写真立て。妻と、満面の笑みを浮かべる息子の翔太。いつもなら、この写真を見て「よし、頑張ろう」と思えたのに、今は直視することすら辛い。写真立てをそっと裏返し、段ボールの底に置いた。
使い込んだマグカップ、後輩からもらった誕生日プレゼントのボールペン、読みかけの技術書、引き出しの奥に入れていた常備薬…。一つ一つ手に取るたびに、ここでの日常がフラッシュバックする。楽しかったこと、苦しかったこと、達成感を味わったこと。それら全てが、色褪せた過去の遺物のように感じられた。
周囲の視線は、依然として健一に集中していた。誰も、何も言わない。声をかける者もいない。それは、同情からなのか、恐怖からなのか、あるいは単なる無関心なのか。健一には、その全てが自分への非難のように感じられた。かつて「頼れる先輩」だったはずの自分が、今は腫れ物のように扱われている。完全な孤立。息が詰まりそうだった。
時折、こらえきれずに涙が滲みそうになるのを、奥歯を噛み締めて耐える。ここで泣き崩れるわけにはいかない。最後の、なけなしのプライドだった。
荷造りは、思ったよりも早く終わった。大した私物は、もともと置いていなかったのだ。会社のPCからは、セキュリティ担当者が手際よくケーブルを抜き、回収していく。健一がアクセス権を持っていたサーバーやシステムのアカウントも、おそらく今頃、次々と停止されているのだろう。15年かけて積み上げてきたものが、数時間で跡形もなく消えていく。
午後4時50分
終業時間まで、まだ1時間以上ある。しかし、健一にできることはもう何もなかった。私物が入った段ボール箱を足元に置き、ただ、空っぽになったデスクの前で、抜け殻のように座っているしかなかった。付き添いの二人は、少し離れた場所で健一を監視するように立っている。
フロアには、キーボードを叩く音、電話の呼び出し音、時折交わされる業務上の会話など、いつものオフィスの音が響いている。しかし、その全てが、まるで分厚いガラスを隔てた向こう側の出来事のように、健一には遠く感じられた。自分だけが、この日常から切り離され、異空間に放り出されたかのようだ。
(これから、どうなるんだろう…)
(妻になんて説明すれば…)
(翔太の顔を、まともに見れるだろうか…)
(住宅ローンは…)
最悪の想像が、次から次へと頭を駆け巡る。懲戒解雇という事実の重みが、じわじわと全身を蝕んでいく。会議室で宣告された時よりも、今この瞬間の方が、より深く絶望を感じていた。周囲の日常が続いているからこそ、自分の転落が際立って感じられるのだ。
時計の針が、拷問のようにゆっくりと進む。早くこの場から立ち去りたい。しかし、まだ終業時間ではない。人事部の社員は、おそらく他の社員への影響を考え、終業時間後に健一をオフィスから出すつもりなのだろう。晒し者にされているような気分だった。
午後5時30分
ようやく、終業時間を告げるチャイムが鳴った。フロアのあちこちで、社員たちが帰り支度を始める音がする。健一は、付き添いの二人に促され、ゆっくりと立ち上がった。段ボール箱を抱える。思ったよりも重く感じた。それは、私物の重さだけではない、これから背負っていくことになるであろう、人生の重みそのものかもしれなかった。
エレベーターホールへと向かう。帰り支度を終えた同僚たちが、遠巻きに健一を見ていた。誰も、近づいてはこない。エレベーターに乗り込み、ドアが閉まる瞬間、最後に見たのは、心配そうにこちらを見つめる田中の顔だった。しかし、健一にはもう、彼に何かを言う気力も、資格もないように思えた。
下降していくエレベーターの中で、健一は固く目を閉じた。ビルの外に出れば、いつもの帰り道が待っているはずだ。しかし、その道はもう、昨日までとは全く違う、暗く、先の見えない道に変わってしまっていた。平凡な日常は、今日の午後、唐突に終わりを告げたのだ。
帰路
午後6時5分
オフィスビルの自動ドアが開き、健一は夕暮れの街へと押し出された。背後でドアが閉まる音は、まるで社会との間にシャッターが下ろされたかのように響いた。付き添っていた人事部の社員は、ビルの中から無言で見送るだけで、外まではついてこなかった。解放された、というよりは、放り出された、という感覚に近い。
西の空は、燃えるようなオレンジ色と、深い藍色が混じり合い、美しいグラデーションを描いていた。昨日までなら、一日の仕事の終わりを告げるその景色に、ささやかな安堵感を覚えただろう。しかし、今日の健一の目には、その美しさすら毒々しく、不吉なものに映った。
抱えた段ボール箱が、ずしりと重い。物理的な重さ以上に、その中身が象徴する「失われたもの」の重みが、健一の肩にのしかかる。行き交う人々は、仕事終わりの解放感や、これから始まるプライベートな時間への期待に満ちた表情をしているように見えた。誰も、段ボール箱を抱えて俯く中年の男が、ほんの数時間前に人生の崖っぷちに立たされたことなど知る由もない。その無関心さが、健一の孤独感を一層深めた。
駅までの道は、いつもと同じはずなのに、まるで初めて歩く場所のように感じられた。足が鉛のように重く、一歩進むごとに、地面に縫い付けられるような感覚に襲われる。ショーウィンドウに映る自分の姿は、疲れ果て、生気を失った、見知らぬ男のようだった。
(これから、どうすればいいんだ…?)
(妻に…美咲になんて言えば…)
(翔太は…まだ小さいのに…)
思考は、暗いループから抜け出せない。良かれと思ってやったことだ、という言い訳は、もはや何の慰めにもならなかった。結果が全て。その言葉が、呪いのように頭の中で繰り返される。シャドーITのリスクを軽視した自分への後悔、会社への不信感、そして、何よりも家族を巻き込んでしまうことへの恐怖と罪悪感が、津波のように押し寄せてくる。
午後6時30分
駅のホームは、帰宅ラッシュでごった返していた。健一は、人々の流れから少し離れた柱の陰に、段ボール箱を置いて立ち尽くした。電車の接近を告げるアナウンスが、やけに大きく聞こえる。
乗り込んだ電車は、座る席もなく、吊り革に掴まるのがやっとだった。周囲の乗客たちの話し声、スマホの画面を覗き込む人々、イヤホンで音楽を聴く若者…。それぞれの日常が、そこにはあった。健一だけが、その輪から弾き出されている。汗と香水の匂いが混じり合った車内の空気が、息苦しい。早くこの空間から抜け出したかったが、自宅へ向かうこの電車に乗っていること自体が、さらなる苦痛への序章に過ぎないことも分かっていた。
窓の外を、見慣れた街の灯りが流れていく。高層マンションの明かり、コンビニの看板、車のヘッドライト…。その一つ一つの光の中に、人々の生活がある。自分も、ついさっきまで、その「普通の生活」の中にいたはずなのに。
(あのツールさえ使わなければ…)
(いや、もっと慎重にパスワード管理をしていれば…)
(そもそも、ちゃんと申請していれば…)
後悔の念が、次から次へと湧き上がってくる。だが、もう遅い。時間は巻き戻せない。失われた信用、キャリア、そしておそらくは、安定した生活。その代償はあまりにも大きかった。
午後7時15分
最寄り駅に到着した。改札を出ると、ひんやりとした夜風が頬を撫でた。少しだけ、現実感が戻ってくる。しかし、それは同時に、これから直面しなければならない現実の重さを、よりはっきりと認識させるものでもあった。
自宅までの道は、駅から歩いて10分ほど。いつもなら、妻の美咲が作ってくれているであろう夕食の匂いを想像したり、翔太がどんな顔で迎えてくれるかを楽しみにしたりしながら歩く道だ。しかし、今日の足取りは、まるで処刑台に向かう罪人のように重かった。
一歩ごとに、心臓が早鐘のように打つ。家の明かりが見えてきた。温かな、オレンジ色の光。それは、健一にとっての「帰る場所」であり、「守るべきもの」の象徴だった。しかし今、その光が、告発の光のように感じられてしまう。
(なんて言おう…)
(「クビになった」…? いや、もっと酷い、「懲戒解雇」だ…)
(理由も…情報漏洩なんて…)
(美咲は、信じてくれるだろうか…? 呆れられるだろうか…? それとも…)
最悪の事態ばかりが頭をよぎる。離婚、家庭崩壊…。考えたくもない未来が、現実味を帯びて迫ってくる。
ついに、自宅のドアの前にたどり着いた。表札には「佐藤」と、控えめな文字が刻まれている。このドアを開ければ、日常が終わる。新しい、苦難に満ちた日々が始まる。
段ボール箱を一旦地面に置き、震える手でポケットから鍵を探す。鍵穴に鍵を差し込む手が、うまく動かない。何度か試して、ようやくカチャリと音がした。
深呼吸を一つ。意を決して、ドアノブに手をかける。
家庭崩壊
「ただいま…」
か細い声に反応して、リビングのドアが開き、息子の翔太が飛び出してきた。
「あ、パパお帰りー!」
満面の笑みで駆け寄ってくる翔太。健一は、その無邪気さに胸が締め付けられ、思わず顔を背けそうになった。段ボール箱を抱え直す。
「翔太、ただいま」
なんとか声を絞り出すが、その声は震えていた。
翔太の後ろから、妻の美咲が姿を現した。しかし、その表情は、健一が覚悟していた以上に冷え切っていた。いつもの「おかえりなさい」という温かい言葉はない。ただ、氷のように冷たい視線で、健一と、彼が抱える段ボール箱を交互に見ている。その目には、怒りとも、軽蔑ともつかない、しかし明らかに拒絶を示す色が浮かんでいた。
「…美咲?」
健一は戸惑いながら声をかけた。何かを察しているのか? いや、それ以上だ。この目は、すでに全てを知っている者の目だ。
「おかえりなさい」
美咲は、感情のこもらない平坦な声で言った。
「…その箱、何?」
「あ、いや、これは…その…」
健一は言葉に詰まる。どう切り出せばいいのか。しかし、美咲は健一の言葉を待たなかった。
「説明なんて、もう要らないわ」
美咲は静かに、しかし有無を言わせぬ口調で続けた。
「今日、会社から書留が届いたの」
健一の心臓が、ドクンと大きく跳ねた。血の気が引いていくのが分かった。
「書留…?」
「ええ。『懲戒解雇通知書』。ご丁寧に、理由まで書いてあったわ。『機密情報の漏洩』ですって」
美咲の言葉は、鋭いナイフのように健一の胸を突き刺した。やはり、知っていたのだ。会社は、本人への通告と同時に、自宅へも通知を送っていたのか。最悪のタイミングだ。いや、どのタイミングであっても、結果は同じだったのかもしれないが。
「美咲、違うんだ、いや、違わないけど、聞いてくれ!あれは…」
健一は必死に弁解しようとした。しかし、美咲は冷たく首を横に振った。
「聞きたくない。あなたが会社のお金を横領したとか、そういうのならまだ…いや、それも許せないけど、情報漏洩って…犯罪じゃないの? 信じられない。あなたがそんなことをするなんて…最低よ」
その声には、深い失望と、裏切られたことへの怒りが込められていた。健一が最も恐れていた反応だった。
「パパ、どうしたの? ママ、怒ってるの?」
翔太が、不安そうな顔で二人を見上げている。場の険悪な空気を、子供なりに感じ取っているのだ。
美咲は、健一から視線を外し、翔太に向かって無理に笑顔を作った。
「翔太、ちょっとママとおばあちゃん家に行こうか」
「え? 今から? なんで?」
翔太はきょとんとしている。
「美咲、待ってくれ! 話し合おう! 俺が悪かった、本当にすまないと思ってる! でも、これからどうするか…」
健一はすがりつくように言った。
しかし、美咲の決意は固かった。彼女は再び健一に冷たい視線を向けた。
「話し合うことなんて何もないわ。懲戒解雇された人と、ましてや情報漏洩なんて起こした人と、これから一緒に生活していくなんて考えられない。住宅ローンだってどうするの? 翔太の将来は? あなたにはもう、何も期待できない」
その言葉は、健一の最後の希望を打ち砕いた。シミュレーションで描かれた最悪のシナリオが、現実のものとして目の前で展開されている。あの時はフィクションだと思っていたのに。
「そんな…一方的に…」
「一方的? あなたが勝手なことをして、私たちを危険に晒したんでしょう? 私と翔太の人生を壊さないで」
美咲はそう言い放つと、リビングの奥へ行き、あらかじめまとめてあったのだろう、小さなスーツケースと翔太のリュックサックを持ってきた。その手際の良さが、彼女の決意の固さを物語っていた。
「翔太、行くわよ」
美咲は翔太の手を強く引いた。
「えー、やだ! パパといる!」
翔太は状況が飲み込めず、ぐずり始めた。健一に助けを求めるように視線を送る。
「翔太…」
健一は息子に何も言ってやれない。父親失格だ。いや、もう父親でいることすら許されないのかもしれない。
「いいから、来るの!」
美咲は半ば強引に翔太を引っ張り、玄関のドアを開けた。
「待ってくれ、美咲! 頼む! 行かないでくれ!」
健一は叫んだが、美咲は一度も振り返らなかった。翔太は泣きながら、何度も後ろを振り返り、「パパ! パパ!」と叫んでいた。
バタン、と無情にドアが閉まる。
一瞬にして、家の中はしんと静まり返った。さっきまでの翔太の泣き声が、まだ耳の奥で反響しているようだ。健一は、その場に崩れ落ちそうになるのを、なんとか堪えた。
リビングには、まだ夕食の準備が途中だったのだろう、食卓の上に食材が置かれたままになっている。温かい家庭の象徴だったはずのその光景が、今はひどく空虚に見えた。
抱えていた段ボール箱が、手から滑り落ちた。ガシャン、と鈍い音がして、中に入れていたマグカップが割れたのかもしれない。しかし、健一にはそれを確かめる気力もなかった。
一人、がらんとした家に残された健一。
懲戒解雇、情報漏洩、そして、妻と子の喪失。
シミュレーションで描かれた転落のシナリオは、今、現実のものとなった。これから始まるであろう、本当の地獄を予感しながら、健一はただ、呆然と立ち尽くすしかなかった。
静寂の夜
午後7時30分
玄関のドアが閉まってから、どれくらいの時間が経っただろうか。健一は、まるで時間が止まったかのような感覚の中で、冷たい玄関の床に膝をつきそうになるのを必死でこらえていた。耳の奥で、まだ翔太の「パパ!」という泣き声がこだましている。現実感が希薄で、まるで悪夢を見ているかのようだ。しかし、床に散らばった段ボール箱の中身――使い慣れた文房具、数冊の専門書、そして無残に割れたマグカップの破片――が、これが紛れもない現実であることを突きつけてくる。
重い体を無理やり起こし、ふらつく足取りでリビングへ向かう。ドアを開けると、そこには先ほどまで家族がいたはずの空間が広がっていた。食卓の上には、美咲が夕食に準備していたであろう、切りかけの野菜とまな板がそのままになっている。翔太が好きだったハンバーグを作るつもりだったのだろうか。その光景が、今はただただ痛々しい。
ソファに、どさりと腰を下ろす。クッションには、まだ美咲が使っていた香水の残り香が微かに漂っている気がした。テレビのリモコンが手の届く場所にあったが、電源を入れる気にはなれなかった。賑やかな音や、他人の幸せそうな姿など、今は見たくも聞きたくもなかった。
家の中は、水を打ったように静まり返っていた。時計の秒針がカチ、カチ、と時を刻む音だけが、やけに大きく響く。その規則的な音が、健一の不規則で乱れた心臓の鼓動を、より一層際立たせた。
(これから、どうなるんだ…?)
(美咲と翔太は、本当に実家に行ったのか? もう二度と、ここには戻ってこないのか?)
(住宅ローン…来月の支払いはどうする? 貯金だって、そんなに余裕はないはずだ…)
(再就職…? 懲戒解雇された人間を、誰が雇ってくれる?)
(情報漏洩…会社から損害賠償を請求されたら…?)
次から次へと、暗い考えばかりが頭をよぎる。まるで底なし沼に引きずり込まれていくようだ。後悔、自己嫌悪、そして未来への底知れぬ恐怖。様々な感情が渦巻き、健一の心を蝕んでいく。
午後9時
空腹感は全くなかった。むしろ、胃が鉛のように重く、何かを口にしたら吐いてしまいそうだった。それでも、何か喉を潤さなければと思い、キッチンへ向かう。冷蔵庫を開けると、缶ビールが数本冷えていた。昨日までは、仕事終わりのささやかな楽しみだったそれが、今は忌まわしいものに見えた。
(酒で紛らわせるか…?)
一瞬そう思ったが、すぐにその考えを打ち消した。酔って現実逃避したところで、目が覚めれば現実は何も変わらない。むしろ、さらに惨めな気分になるだけだろう。結局、健一は冷蔵庫からミネラルウォーターのペットボトルを取り出し、味気なく一口飲んだだけだった。
リビングに戻り、再びソファに沈み込む。窓の外は、すっかり暗くなっていた。近隣の家々の窓には明かりが灯り、家族団らんの温かい光景が繰り広げられているのだろう。その光が、今の健一には眩しすぎた。カーテンを閉め、外界からの光を遮断する。部屋の中は、間接照明の薄暗い光だけになり、健一の孤独を一層濃くした。
床に散らばった段ボール箱の中身が目に入る。割れたマグカップは、翔太が父の日にプレゼントしてくれたものだった。その破片を見るたびに、罪悪感が胸を締め付ける。片付けなければ、と思うのに、指一本動かす気力が湧いてこない。まるで、自分の人生そのものが、あのマグカップのように粉々に砕け散ってしまったかのようだった。
午後11時
時間だけが、無情に過ぎていく。健一はソファの上で、ただただ虚空を見つめていた。誰かに連絡しようかとも考えた。両親、数少ない友人…。しかし、何を話せばいいのか。懲戒解雇されたこと、妻と子に出ていかれたこと…。そんな惨めな報告ができるはずもなかった。結局、スマートフォンを手に取ることすらできなかった。社会的な繋がりが、ぷつりと断ち切られたような感覚。
もう寝よう、と思った。眠ってしまえば、少しはこの苦しみから解放されるかもしれない。しかし、寝室へ向かう足取りは重かった。寝室には、美咲と使っていたダブルベッドと、その隣に置かれた翔太の小さなベッドがある。そこには、まだ家族の温かい気配が色濃く残っている。それが、今の健一には耐え難い苦痛だった。
電気を消し、ベッドに横になる。シーツからは、まだ美咲の匂いがするような気がした。隣の翔太のベッドからは、寝息の代わりに、空虚な静寂だけが伝わってくる。
目を閉じても、眠気は全く訪れなかった。まぶたの裏には、人事部長の冷たい顔、同僚たちの好奇の視線、そして、泣きながら去っていった翔太の顔と、冷え切った美咲の目が繰り返し浮かんでくる。
(シミュレーション通りだ…)
あの時、最悪の事態として想像したシナリオが、寸分違わず現実になっている。あの時は、どこか他人事のように感じていたのに。まさか自分が、こんな状況に陥るなんて。
後悔しても、時間を巻き戻すことはできない。
謝罪しても、失った信用は戻らない。
祈っても、家族が帰ってくる保証はない。
暗闇の中で、健一はただ、天井の一点を見つめ続けた。静寂が、まるで重石のように体の上にのしかかってくる。これから始まるであろう、長く、暗いトンネルのような日々を思い、健一は身動き一つできずに、ただただ夜が更けていくのを待つしかなかった。眠れない夜は、まだ始まったばかりだった。
忍び寄る困窮
あの日、美咲と翔太が家を出て行ってから、1ヶ月が過ぎようとしていた。最初の数日は、茫然自失として、ただ時間が過ぎるのを待つだけだった。しかし、現実は容赦なく健一に襲いかかってきた。それは、静かに、しかし確実に彼の生活を蝕む「経済的な困窮」という名の怪物だった。
貯金の目減り
健一は、震える手でスマートフォンの銀行アプリを開いた。画面に表示された普通預金の残高は、98万3,450円。ついに、100万円の大台を割り込んでいた。解雇される前は、ボーナスも合わせればもう少し余裕があったはずだが、住宅ローンの頭金や日々の生活費で、思った以上に貯蓄は目減りしていたのだ。そして今、収入が完全に途絶えた状態で、この残高はまさに命綱だった。しかし、その命綱は、驚くべき速さで短くなっていった。
容赦ない支出
まず、食費。当初は自炊して切り詰めようとしたが、精神的な落ち込みから料理をする気力も湧かず、結局コンビニ弁当やスーパーの割引された惣菜に頼ることが増えた。それでも、一人分の食費とはいえ、確実に貯金は減っていく。
次に、光熱費と通信費。家に引きこもりがちになったことで、電気代は以前よりかさんでいるかもしれない。スマートフォンの通信費も、情報収集や求人検索(まだ本格的には始められていないが)に必要不可欠だ。請求書を見るたびに、ため息が出た。
そして、公的な負担が重くのしかかる。会社を辞めたことで、健康保険は国民健康保険に切り替わった。送られてきた納付書に記載された金額を見て、健一は愕然とした。前年の所得に基づいて計算されるため、無職になったばかりの健一にとっては、あまりにも高額だった。国民年金も同様だ。慌てて役所に免除申請に行ったが、手続きは煩雑で、すぐには承認されなかった。「審査に時間がかかります」「とりあえず、今月分はこちらの金額で…」事務的な対応に、心が折れそうになる。一部負担でも、今の健一には厳しい出費だった。
最大の重圧:住宅ローン
だが、それら全てを合わせたよりも重く健一の肩にのしかかっていたのが、住宅ローンだった。月々10万円。安定した収入があった頃は、少し負担に感じつつも、マイホームという夢の対価として支払えていた。しかし、今は違う。通帳の残高が減っていく中で、毎月決まった日に10万円が引き落とされる恐怖。それは、まるで時限爆弾のカウントダウンを聞いているような心地だった。引き落とし日が近づくたびに、夜中に目が覚め、言いようのない不安に襲われた。あと何回、この支払いが続けられるだろうか?
追い打ち:養育費の督促
さらに健一の精神を削ったのが、養育費の問題だった。美咲側から代理人弁護士を通じて、正式に養育費の請求が来ていた。月々5万円。今の健一には到底支払える金額ではない。最初の1ヶ月は、なけなしの貯金からなんとか支払ったが、今月はもう無理だった。
すると、携帯電話に見慣れない番号からの着信が増えた。出てみると、案の定、弁護士事務所からの事務的な声だった。
「佐藤様、今月分の養育費のお支払いが確認できておりませんが」
「いつ頃お支払いいただけますでしょうか?」
その冷静な口調が、逆に健一を追い詰めた。支払えないことへの罪悪感、翔太への申し訳なさ、そして、どうしようもない自分の不甲斐なさ。電話が鳴るたびに、心臓が跳ね上がった。時には、留守電に冷たいメッセージが残されていることもあった。
忍び寄る影
部屋は荒れ放題だった。シンクには汚れた食器が溜まり、床には脱ぎっぱなしの服や空のペットボトルが転がっている。かつて家族で笑い声が響いたリビングは、今はただ埃っぽく、薄暗い。健一自身も、髭は伸び放題、着ている服も数日同じものだった。鏡に映る自分の姿は、まるで別人のようにやつれていた。
通帳の数字が減るたびに、請求書が届くたびに、督促の電話が鳴るたびに、健一の心は少しずつ削られていった。まだ90万円以上ある、と思う反面、住宅ローンだけであと9ヶ月しか持たない、という現実がすぐそこに見えている。再就職活動を始めなければならないことは分かっている。しかし、懲戒解雇という重い十字架を背負って、一体どこが雇ってくれるというのか。行動を起こす前から、諦めの気持ちが心を支配していた。
経済的な困窮は、単にお金がないという物理的な問題だけではなかった。それは、将来への希望を奪い、精神的な安定を破壊し、人間としての尊厳すら脅かす、静かで、しかし恐ろしい怪物だった。健一は、その怪物の影が、すぐ背後まで忍び寄ってきているのを感じていた。
閉ざされた扉
午前7時
アラームが鳴る前に、重いまぶたをこじ開けた。カーテンの隙間から差し込む朝日は、かつては希望の光だったが、今はただ、また成果のない一日が始まることを告げる合図のように感じられた。健一は、軋む体をゆっくりと起こし、ベッドサイドに置いたままのミネラルウォーターを一口飲んだ。喉がカラカラだった。
寝室を出てリビングへ向かう。散らかった部屋は昨日と何も変わっていない。片付ける気力も湧かず、ソファに座り込むと、ノートパソコンを開いた。これが、ここ数週間の健一の朝のルーティンだった。
午前8時:求人サイトの海へ
ブックマークしてある複数の転職サイトを巡回する。新着求人をチェックするが、目に飛び込んでくるのは「経験者優遇」「マネジメント経験必須」といった、今の健一には縁遠い言葉ばかりだ。それでも、わずかな可能性を信じて、キーワード検索を繰り返す。「事務」「営業」「管理」…。
ふと、一件の求人が目に留まった。中小企業の社内SE。業務内容には、健一が前職で培ってきたスキルの一部が活かせそうな記述がある。「これなら…」一瞬、希望が胸をよぎる。しかし、応募資格の欄に小さく書かれた「※円満退職者に限る」という一文を見つけ、心臓が冷たくなるのを感じた。
午前10時:履歴書との格闘
気を取り直し、履歴書と職務経歴書のテンプレートを開く。問題は「退職理由」の欄だ。正直に「懲戒解雇(情報漏洩のため)」と書けば、その時点で書類選考を通過する可能性はゼロに近いだろう。それは、これまでの数十社への応募で嫌というほど思い知らされていた。
「一身上の都合」と書くか? しかし、離職票には「重責解雇」の文字が刻まれている。面接に進めたとしても、必ず聞かれるだろう。嘘をつき通せる自信はないし、もしバレたら、それこそ信用を失う。
結局、当たり障りのないように「会社都合により退職」とだけ書き、職務経歴書には具体的なプロジェクト実績を並べることで、なんとかアピールしようと試みる。だが、書きながらも、虚しさが募るばかりだった。送信ボタンを押す指が、鉛のように重い。今日も数社に応募したが、期待はほとんどしていなかった。
午後1時:ハローワークの現実
昼食は、冷蔵庫に残っていた食パンをかじっただけだった。午後からは、重い足取りでハローワークへ向かった。ネットの求人だけでは限界があると感じていたからだ。
相談窓口で、担当者にこれまでの経緯を正直に話した。懲戒解雇であること、その理由が情報漏洩であること。担当者は同情的な表情を見せながらも、言葉は厳しかった。
「佐藤さん、正直に申し上げますと、かなり厳しい状況です。特に情報漏洩となると、企業側が最も警戒する事案の一つですから…」
「信用問題になりますので、管理部門やIT関連の職種は、まず難しいと考えた方がいいでしょう」
「年齢も…42歳となると、未経験の職種への転職も簡単ではありません」
いくつか、条件に合いそうな求人を紹介してくれたが、どれも給与水準は前職の半分以下、あるいは契約社員やアルバイトだった。それでも、贅沢は言えない。紹介状をもらい、その場で数社に応募手続きをしたが、担当者の曇った表情が、結果を暗示しているように思えた。
午後4時:届く「お祈りメール」
帰宅し、郵便受けを確認するが、あるのは請求書ばかり。パソコンを開き、メールをチェックすると、受信トレイには数件の新着メールがあった。件名を見れば、内容はすぐに分かった。
「選考結果のご連絡」
「今後のご活躍をお祈り申し上げます」
「件名:選考結果のご連絡
佐藤 健一 様
この度は、ハローワークを通じて弊社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございました。
また、先日はお忙しい中、面接にお越しいただき、重ねて御礼申し上げます。
佐藤様のこれまでのご経験や、仕事に対する熱意につきまして、大変興味深く拝見・拝聴いたしました。
社内で慎重に選考を重ねました結果、誠に残念ながら、今回は貴意に沿いかねる結果となりました。
ご期待に沿えず大変申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今回の募集におきましては、佐藤様のご経歴や適性などを総合的に検討させていただきましたが、弊社の求める経験や資質と合致するには至りませんでした。
お預かりいたしました応募書類につきましては、弊社規定に基づき、責任をもって破棄させていただきます。
末筆ではございますが、佐藤様の今後のご健勝と、より一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
敬具」
テンプレート通りの丁寧な言葉が、今は心を抉るナイフのように感じられた。数十社応募して、面接にすらたどり着けたのは、ほんの数社。その数少ない面接でも、懲戒解雇の理由を正直に話した途端、面接官の表情が曇り、あからさまに警戒された。「なぜ情報漏洩を?」「管理体制はどうなっていたのですか?」詰問に近い質問に、しどろもどろになるしかなかった。結果は、言うまでもなく不採用だった。
午後6時:「未経験可」の壁
もう、プライドなどかなぐり捨てるしかなかった。求人サイトで「未経験可」「年齢不問」と検索し、倉庫での軽作業や、清掃員のアルバイトに応募してみた。これなら、さすがに大丈夫だろう、と。
しかし、数日後にかかってきた電話で、健一はさらなる現実に打ちのめされる。
「大変申し訳ありませんが、今回は他の方に決まりまして…」
「募集は充足いたしましたので…」
理由は明確には言われない。しかし、電話口の相手のわずかな躊躇いや、言葉の端々から、「42歳で未経験」「前職が…」というニュアンスが透けて見える気がした。若い労働力が欲しいのだろう。あるいは、懲戒解雇という経歴が、どこかで引っかかっているのかもしれない。
午後9時:絶望の夜
その日も、何の成果も得られないまま、夜が更けていく。リビングの電気もつけず、健一はソファに深く沈み込んでいた。パソコンの画面には、相変わらず求人サイトが表示されているが、もう文字を追う気力もない。
頭の中では、減り続ける貯金の残高、来週に迫った住宅ローンの引き落とし日、そして、滞納している養育費のことがぐるぐると回っている。数十社、いや、もうすぐ百社に届くかもしれない。それだけ応募しても、どこからも必要とされない。社会から完全に拒絶されているような感覚。
「どうすればいいんだ…」
暗闇の中で、健一は力なく呟いた。その声は、静まり返った部屋に虚しく響き、誰に届くこともなく消えていった。再就職活動の惨敗は、健一から最後の希望すら奪い去ろうとしていた。
砕け散る最後の欠片(単発バイトも惨敗)
再就職活動が完全に暗礁に乗り上げてから、数日が過ぎた。貯金残高は、もはや80万円を切ろうとしている。住宅ローンの引き落とし日は刻一刻と迫り、養育費の督促電話は、もはや着信拒否するしかなくなっていた。焦燥感と絶望感が、健一の心を黒く塗りつぶしていく。
「とにかく、今日、明日の金を稼がないと…」
もはや、正社員はおろか、長期の仕事を探す余裕すらなかった。健一は、最後の手段として、日雇いの派遣バイトに登録することにした。スマートフォンの小さな画面で、「日払い」「即日勤務可」といったキーワードで検索し、ヒットした派遣会社に震える手で電話をかけた。
翌日、指定された事務所へ向かう。薄暗い雑居ビルの一室。壁には、「安全第一」「時間厳守」といった標語が貼られている。周りには、健一よりもずっと若い、あるいは逆に年配の、様々な事情を抱えていそうな人々が数人いた。スーツ姿の健一は、明らかに場違いだった。簡単な説明を受け、身分証を提示し、登録用紙に記入する。職歴の欄は、当たり障りなく「IT関連企業勤務」とだけ書いた。懲戒解雇の事実は、ここでは伏せておくしかなかった。
最初の試練:倉庫作業
最初に紹介されたのは、郊外にある巨大な物流倉庫でのピッキング作業だった。翌朝、始発電車に乗り、指定された倉庫へ向かう。朝礼では、威勢のいいリーダーが大声で指示を飛ばし、若い作業員たちがそれに返事をする。健一は、その輪の中にうまく入れず、隅の方で小さくなっていた。
作業が始まると、その過酷さを思い知らされた。ハンディターミナルに表示される指示に従い、広大な倉庫内を歩き回り、指定された商品を棚から探し出してカートに乗せる。単純作業だが、とにかく歩く距離が長い。普段デスクワークしかしてこなかった健一の足は、午前中のうちに棒のようになった。重い荷物を持ち上げるたびに、腰に鈍い痛みが走る。
周りの作業員たちは、黙々と、しかし驚くほど速いペースで作業をこなしていく。健一は明らかに遅れをとっていた。焦れば焦るほど、商品の場所を間違えたり、数量を誤ったりする。リーダーらしき人物から、「おい、そこの新人!もっとテキパキ動け!」と怒鳴られ、体が竦んだ。昼休憩の時間、他の作業員たちはグループになって談笑していたが、健一に話しかけてくる者は誰もいなかった。孤独感が、じわじわと心を蝕んでいく。
その日の作業が終わる頃には、健一は全身汗だくで、疲労困憊していた。ふらふらになりながら帰路につき、家のドアを開けた瞬間、ソファに倒れ込んだ。日給8000円。その金額を得るために、これほどの肉体的・精神的苦痛を味わわなければならないのか。前職の給料がいかに恵まれていたかを、皮肉にも痛感させられた。
二日目の壁
翌朝、健一はベッドから起き上がることができなかった。全身が鉛のように重く、特に腰と足の痛みがひどい。それ以上に、心が完全に折れていた。あの倉庫へ行くことを考えると、吐き気すら催した。
「無理だ…もう行けない…」
震える手でスマートフォンを掴み、派遣会社の担当者に電話をかける。
「すみません、体調が悪くて…本日、お休みさせてください…」
声はか細く、自分でも情けなくなるほどだった。担当者は事務的な口調で了承したが、その声には「またか」というような響きが感じられた気がした。
二度目の試練:交通整理
数日後、少し体調が回復した健一は、別のバイトを試みることにした。今度は、工事現場での交通整理だった。倉庫作業よりは体力的負担が少ないかもしれない、と淡い期待を抱いていた。
しかし、これも甘かった。ヘルメットを被り、指定されたベストを着て、誘導灯を持つ。単純な仕事に見えたが、炎天下の中、アスファルトの照り返しを受けながら一日中立ちっぱなしというのは、想像以上に過酷だった。車が途切れる時間はほとんどなく、集中力を維持しなければならない。単調な作業が、逆に精神をすり減らしていく。
ここでも、健一は孤立していた。他の作業員たちは、休憩時間にタバコを吸いながら、健一には分からないような現場特有の話題で盛り上がっている。健一が話しかけようとしても、どこか壁があるような、よそよそしい態度を取られた。彼らにとって、健一は「すぐに辞める、使えない奴」に見えているのかもしれない。
三日目の午後、突然の雨に見舞われた。雨合羽を着て作業を続けたが、体は冷え切り、誘導灯を持つ手がかじかむ。惨めだった。なぜ、自分はこんなところで、こんな仕事をしているのだろうか。情報漏洩さえしなければ、今頃は…後悔と自己嫌悪が、冷たい雨と共に心に染み込んできた。
その日の帰り道、健一は派遣会社に電話をかけ、「もう続けられません」と告げた。
残されたもの
結局、短期バイトで健一が得られた収入は、わずか数万円にも満たなかった。それ以上に失ったものは大きかった。わずかに残っていた体力、そして、「まだやれるかもしれない」という最後の希望の欠片。
慣れない肉体労働、精神的な落ち込み、そして、どこへ行っても感じる孤立感。短期バイトという、社会との最後の繋がりすら、健一は維持することができなかった。
部屋に戻り、力なくベッドに倒れ込む。通帳の残高は、さらに減っている。もう、打つ手はないのだろうか。暗闇の中で、健一はただ、天井の一点を虚ろに見つめることしかできなかった。経済的な困窮は、もはや避けられない破滅への序章のように思えた。
迫りくる赤信号(ローンが…)
短期バイトの試みが無残な失敗に終わってから、さらに数週間が過ぎた。健一の生活は、もはや破綻寸前だった。収入は完全にゼロ。日々の食費すら切り詰め、電気やガスも必要最低限しか使わないようにしていたが、それでも貯金は驚くべき速さで減っていった。
スマートフォンの画面に表示されたネットバンキングの残高は、ついに10万円を切っていた。それは、健一にとって、崖っぷちに立たされたことを意味していた。なぜなら、来週には、あの忌まわしい住宅ローンと養育費の引き落とし日が迫っているからだ。月々の返済額は、合わせて約15万円。もはや、どうあがいても支払うことは不可能だった。
引き落とし日が近づくにつれて、健一の胸は鉛を飲み込んだように重くなっていった。夜はほとんど眠れず、浅い眠りの中で、銀行のロゴマークや、冷たいATMの画面が繰り返し現れる悪夢にうなされた。食事も喉を通らず、体重は目に見えて落ちていった。
そして、運命の引き落とし日。健一は、恐る恐るネットバンキングにログインした。画面には、無情にも「残高不足のため、引き落としできませんでした」という赤い文字が表示されていた。分かっていたこととはいえ、全身から血の気が引くのを感じた。ついに、やってしまった。社会的な信用を、また一つ失ってしまったのだ。
その数日後、郵便受けに、見慣れない封筒が入っているのを見つけた。差出人は、住宅ローンを組んでいる銀行だった。震える手で封を開けると、中には「お支払いのお願い」と題された督促状が入っていた。丁寧な言葉遣いではあったが、内容は明確だった。
「期日までにお支払いいただけない場合、延滞損害金が発生いたします」
「至急、ご入金をお願いいたします」
といった文言が、健一の目に突き刺さる。
それから数日後、今度は見慣れない番号から電話がかかってきた。恐る恐る出てみると、それは銀行のローンセンターからだった。
「佐藤様でいらっしゃいますか?AB銀行の工藤と申します。先日の住宅ローンのお引き落としができておりませんが、ご入金の予定はいかがでしょうか?」
冷静で事務的な口調だったが、健一にはそれが、まるで罪人を尋問する声のように聞こえた。
「あ…、いえ、その…、ちょっと今、手元不如意で…」
しどろもどろに答えるのが精一杯だった。担当者は、「そうですか。では、いつ頃ご入金いただけそうでしょうか?」と畳み掛けてくる。明確な返答などできるはずもなく、「…分かり次第、こちらから連絡します」と、か細い声で答えて電話を切った。
電話を切った後も、心臓は激しく波打ち、冷たい汗が背中を伝った。電話の着信音が鳴るたびに、ビクッと体が跳ねるようになった。知らない番号からの着信は、すべて銀行からの督促のように思え、電話に出ることすら恐怖になった。
督促状は、その後も定期的に届くようになった。最初は「お支払いのお願い」だったタイトルが、「督促状」に変わり、そして「最終通告」へと、その深刻度を増していった。文面も次第に厳しくなり、「法的措置」「期限の利益喪失」「競売」といった、恐ろしい言葉が並ぶようになった。
電話も、日に日に頻度を増していった。最初は日中だけだったものが、夕方にもかかってくるようになり、時には担当者を変えて何度もかかってくることもあった。健一は、もはや電話に出る勇気もなく、着信音を消し、ただスマートフォンの画面が光るのを、息を殺して見つめるだけだった。
部屋に閉じこもり、カーテンを閉め切ったまま、健一はただ時間が過ぎるのを待つことしかできなかった。銀行からのプレッシャーは、目に見えない巨大な手に首を絞められているような感覚だった。精神は限界に近づきつつあり、思考はまとまらず、ただ漠然とした恐怖と絶望感だけが、心を支配していた。貯金が底をついたことは、単なる経済的な問題ではなく、健一の精神を破壊する、確実な一歩となっていた。
予言の鏡
部屋の中は、もはや生活空間とは呼べない有様だった。コンビニ弁当の空き容器やペットボトルが床に散乱し、脱ぎっぱなしの服が小さな山を作っている。カーテンは閉め切られ、昼間だというのに薄暗い。空気は淀み、埃っぽい匂いが鼻をついた。健一自身も、何日も風呂に入っておらず、無精髭が伸び放題だった。 生気のない目で、ただ壁の一点をぼんやりと見つめていた。
銀行からの督促の電話は、もう何日も無視し続けている。郵便受けを覗くことすら怖い。ただ、時間が過ぎるのを待つだけの日々。思考は停止し、感情も麻痺しかけていた。
その時、ふと、机の上に置かれたノートパソコンが目に入った。最後に起動したのはいつだったか、もう思い出せない。何をするでもなく、吸い寄せられるようにパソコンの前に座り、電源を入れた。鈍い起動音の後、見慣れたデスクトップ画面が現れる。
マウスを動かし、ウェブブラウザを開く。ブックマークバーに並んだアイコンの中に、見慣れたロゴがあった。「Felo」。あの日、まだ自分が会社員で、未来への不安を漠然と抱えながらも、どこか他人事のようにAIと対話していた頃に使っていたツールだ。
クリックすると、過去のチャット履歴が一覧で表示された。その中に、ひときわ重い響きを持つタイトルがあった。
「情報漏洩による懲戒解雇後の最悪の転落シミュレーション」。
そうだ、あの時はGemini 2.5 Proとかいう、別の高性能AIとも連携して、かなり詳細なシミュレーションをやったんだったな…。好奇心というよりは、もはや自傷行為に近い感覚で、その履歴を開いた。
画面には、過去の自分とAIたちのやり取りが、生々しく表示された。
『Felo: 懲戒解雇、退職金不支給、失業保険給付制限という状況下で、経済的に困窮していくシナリオをシミュレーションします。Gemini 2.5 Pro、関連する統計データや類似ケースからの情報を補足してください。』
『Gemini 2.5 Pro: 承知しました。特に40代男性、持ち家(ローンあり)、妻子ありの場合、経済的ダメージは深刻化しやすい傾向にあります。貯蓄額にもよりますが、数ヶ月で生活費が枯渇するケースも想定されます。』
スクロールしていくと、さらに具体的な描写が目に飛び込んできた。
『Felo: 再就職活動が難航した場合、日雇い労働などで糊口をしのぐ試みも考えられますが、精神的・肉体的負担から継続は困難になる可能性があります。』
『Gemini 2.5 Pro: その結果、収入が途絶え、住宅ローンの支払いが滞る可能性が非常に高いです。最初の数ヶ月は銀行からの督促状や電話が主ですが、次第に内容は厳しくなり、精神的に追い詰められる状況が予測されます。』
『Felo: 「法的措置」「期限の利益喪失」「競売」といった言葉が現実味を帯びてきます。この段階での精神的ストレスは計り知れません。』
健一は、画面に表示される文字を、まるで初めて見るかのように見つめていた。あの時、このシミュレーションを見ていた自分は、どこかで「これはあくまで仮定の話だ」「自分はこうはならない」と思っていたはずだ。だが、現実はどうだ?画面に書かれている言葉の一つ一つが、寸分違わず今の自分の状況を言い当てている。
「…予言かよ」
乾いた笑いが、かすかに漏れた。AIが予測した「精神的に追い詰められる状況」の、まさに渦中に自分がいる。パソコンの画面の青白い光が、健一のやつれ、絶望に染まった顔を無機質に照らし出していた。
あの時、もっと真剣にこのシミュレーションを受け止めていれば?いや、そもそも情報漏洩なんて起こさなければ…。後悔が、鈍い痛みとなって胸を締め付ける。
画面には、さらに続くシミュレーションの文字が見えた。「社会的孤立」「人間関係の断絶」「住居喪失」…。もはや、それを読み進める気力もなかった。パソコンの電源を乱暴に落とし、再び部屋の暗闇に身を沈める。
AIが示した最悪のシナリオは、もはや「仮定」ではなかった。それは、健一が今まさに歩んでいる、破滅への道筋そのものだったのだ。
予言の鏡(続き)
自嘲的な笑いはすぐに消え、健一の顔からは表情が抜け落ちていた。まるで、自分の未来の設計図を、冷徹な第三者によって突きつけられているかのようだ。マウスホイールを回す指が、わずかに震えている。画面はさらに下へとスクロールし、忌まわしい「フェーズ3」の文字が目に飛び込んできた。
『フェーズ3:社会的孤立と住居喪失』
『人間関係の断絶: 親族や数少ない友人に窮状を訴えようとするが、「自業自得だ」「お金は貸せない」と突き放される(最悪のケース)。あるいは、連絡を取ること自体が億劫になり、次第に誰とも連絡を取らなくなる。社会的に完全に孤立していく。』
健一は息を呑んだ。まだ、誰かに助けを求めてはいない。だが、心のどこかで、最後の望みとして、実家の親や、数少ない友人の顔を思い浮かべていた。しかし、このシミュレーションは、その淡い期待すら打ち砕く。情報漏洩という不祥事、そして懲戒解雇。世間の目は冷たい。「自業自得」。その言葉が、脳内で反響する。きっと、そう言われるだろう。連絡する気力すら、もう湧いてこなかった。すでに、自分は孤立への道を歩み始めているのだ。
『家の差し押さえ: 住宅ローンの滞納が3ヶ月を超え、銀行は保証会社に代位弁済を請求。保証会社から一括返済を求められるが、支払えるはずもなく、家は差し押さえられ、競売にかけられることが決定する。裁判所からの通知がポストに投函される。』
心臓が、嫌な音を立てて跳ねた。滞納は、まだ1ヶ月目だ。だが、このままいけば、3ヶ月などあっという間だろう。「差し押さえ」「競売」。その言葉の持つ破壊的な響きに、全身が粟立った。裁判所からの通知…。想像しただけで、吐き気がした。この家、妻と息子と笑い合った思い出が詰まったこの家が、赤の他人に売り払われる?
『競売と残債: 家は市場価格よりかなり低い価格で落札される。落札代金はローン残高(1000万円弱)に全く届かず、500万円以上の借金だけが残る。自己破産も考えるが、弁護士費用が捻出できない。』
『強制退去: 競売後、落札者から立ち退きを求められる。期限までに家を出なければならず、文字通り路頭に迷う。家財道具もほとんど処分せざるを得ない。』
家を失うだけでなく、さらに莫大な借金が残る。そして、強制退去。路頭に迷う…。健一は、思わずパソコンから顔を背けた。荒れ果てた自分の部屋が、やけに広く、そして冷たく感じられた。ここすら、やがて失われるのか。
それでも、何か強迫観念に駆られるように、再び画面に目を戻した。スクロールは止まらない。まるで、破滅へのカウントダウンを見せつけられているようだ。
『フェーズ4:セーフティネットからの脱落と心身の悪化』
『住居不定: 家を失い、ネットカフェや24時間営業のファミレスを転々とする生活が始まる。所持金はほとんどなく、食事も満足に取れない。清潔な状態を保つことも難しくなる。』
ネットカフェ難民。ニュースで見たことはあったが、自分がそうなるとは考えたこともなかった。温かい布団も、シャワーも、当たり前だった日常が、遠い過去のように思えた。
『生活保護申請の壁: 最後の頼みの綱として役所に生活保護を申請に行く。しかし、「まだ働ける年齢でしょう」「仕事を探す努力が足りない」「住所不定では申請を受け付けにくい」などと言われ、申請が受理されない、あるいは手続きが長期化する(最悪のケース)。申請に必要な書類を揃える気力も失せていく。』
最後のセーフティネットすら、容易には掴めないのか。役所の冷たい対応、煩雑な手続き…。今の自分に、そんな気力があるだろうか?いや、ないだろう。絶望が、じわじわと全身を蝕んでいく。
『健康状態の悪化: 不規則な生活、栄養不足、ストレス、絶望感から、心身ともに急速に衰弱していく。持病が悪化したり、うつ病を発症したりする。しかし、健康保険料を払えず(あるいは資格喪失)、病院に行くこともできない。風邪をこじらせても、市販薬を買うお金もない。』
『精神的な荒廃: 将来への希望を完全に失い、自暴自棄になる。わずかな金銭で安酒を買い、公園などで時間を潰すようになる。身なりにも構わなくなり、周囲から避けられる存在になっていく。思考力も低下し、状況を改善するための行動を起こす気力も湧かない。』
もはや、今の自分と大差ないのではないか?健一は、自分の薄汚れたTシャツを見下ろした。最後に鏡を見たのはいつだったか。思考力も、確かに低下している。ただ、無気力に時間が過ぎるのを待っているだけだ。安酒に逃げる姿が、容易に想像できた。
そして、ついに最後のフェーズが表示された。
『フェーズ5:最悪の末路』
『路上生活: ネットカフェに泊まる金もなくなり、公園のベンチや駅の軒下などで夜を明かすようになる。寒さや空腹、病苦に苛まれる日々。』
『社会からの完全な断絶: 誰からも助けを得られず、社会との接点も完全に失われる。存在しているのかどうかすら、誰にも気にされない状態。』
『最終的な結末: 栄養失調、病気の悪化、あるいは冬場の凍死、不慮の事故などにより、誰にも看取られることなく路上で命を落とす。発見されたとしても、身元不明者として処理される可能性もある。』
健一は、画面を凝視したまま、動かなくなった。涙も出なかった。ただ、体の奥底から、這い上がってくるような冷たい感覚があった。それは恐怖を超え、諦念に近いものかもしれなかった。
「…これが、俺の未来か」
呟きは、誰に聞かれることもなく、薄暗い部屋に吸い込まれていった。パソコンの画面に映る冷徹な文字は、もはや単なるシミュレーションではなかった。それは、健一自身の墓碑銘のように、重く、そして静かに、彼の未来を宣告していた。
孤独の深淵
あれから、季節は容赦なく巡っていた。窓の外に見える街路樹は、かつての鮮やかな緑を失い、くすんだ黄色や赤茶色に染まっている。冷たい風が、隙間から吹き込み、部屋の淀んだ空気をわずかに揺らした。
健一は、部屋の隅で膝を抱えて座っていた。数カ月前、あの忌まわしいシミュレーションを見た時よりも、さらに痩せこけ、目の下の隈は深く刻まれている。伸び放題だった髭は、もはや彼の顔の一部となり、生気のない瞳だけが、虚空を彷徨っていた。
床に散らばるゴミは増え、食べかけのカップ麺の容器からは、酸っぱい匂いが漂っている。電気は止められていないが、日中でも薄暗いのは、カーテンを開ける気力すらないからだ。水道もまだ使える。それが、かろうじて彼をこの部屋に繋ぎ止めている最後のライフラインだった。
『人間関係の断絶: 親族や数少ない友人に窮状を訴えようとするが、「自業自得だ」「お金は貸せない」と突き放される(最悪のケース)。あるいは、連絡を取ること自体が億劫になり、次第に誰とも連絡を取らなくなる。社会的に完全に孤立していく。』
あのシミュレーションの一文が、亡霊のように健一の思考にまとわりつく。
数カ月前、まだわずかな貯金が残っていた頃、彼は一度だけ、スマートフォンの連絡先リストを開いたことがあった。震える指で、実家の番号をタップしようとした。だが、できなかった。母親の心配そうな声、父親の落胆した顔を想像すると、指が動かなかった。「健一、お前、何をやったんだ」。その声が聞こえる気がした。
数少ない友人たちの名前も、ただ眺めるだけだった。彼らには彼らの生活がある。家庭があり、仕事がある。こんな惨めな自分を、誰が受け入れてくれるだろうか。「金なら貸せないぞ」。そう言われるのが怖かった。いや、それ以上に、彼らの同情や憐れみの視線に耐えられそうになかった。
結局、健一は誰にも連絡を取らなかった。いや、取れなかった。シミュレーションが予測した通り、「連絡を取ること自体が億劫に」なり、気力は完全に失せていた。
スマートフォンの着信履歴は、銀行からの督促と、いくつかの知らない番号だけが並んでいる。かつて頻繁に鳴っていた友人からの着信や、妻からのメッセージ通知は、もう何ヶ月も見ていない。バッテリーはとっくに切れ、充電する気にもなれず、今はただの文鎮と化して机の上に転がっている。
社会との繋がりは、ほぼ完全に断たれた。コンビニで最低限の食料を買うとき、店員と交わす「…円です」「…はい」という短い言葉だけが、彼に残された唯一のコミュニケーションだった。それすらも、億劫で、苦痛だった。人々の視線が、自分を値踏みし、蔑んでいるように感じられた。
「自業自得…」
誰に言われたわけでもない。だが、その言葉は、健一自身の内側から、繰り返し響いてくる。あの時、安易な考えでシャドーITに手を出さなければ。あの時、もっと慎重に行動していれば…。後悔は、もはや何の役にも立たないと分かっていながら、寄生虫のように彼の心を蝕み続ける。
部屋の静寂が、耳に痛い。かつては、息子の笑い声や、妻との何気ない会話が満ちていた空間。今は、ただ健一の浅い呼吸と、時折聞こえる外の車の音だけが響く。
彼は、完全に一人だった。シミュレーションが示した「社会的孤立」は、数カ月という時間をかけて、じわじわと、しかし確実に現実のものとなっていた。それは、まるでゆっくりと水の中に沈んでいくような、息苦しく、逃れようのない感覚だった。
窓の外では、枯葉が一枚、また一枚と、力なく地面に落ちていった。
赤紙の宣告
季節は晩秋へと移ろい、空気は日に日に冷たさを増していた。健一の世界は、しかし、季節の変化とは無関係に、色褪せたモノクロームのままだった。部屋に引きこもり、時間の感覚はとうに麻痺している。朝か夜かも曖昧で、ただ空腹を感じればコンビニへ行き、眠くなれば床に転がる。そんな日々が、どれだけ続いただろうか。
住宅ローンや養育費のことなど、もう彼の意識の片隅にも追いやられていた。最初の頃は、銀行からの電話や督促状に怯えていた。だが、それも繰り返されるうちに、日常のノイズの一部と化してしまった。電話は無視し、郵便物は開封せずに積み上げる。見てもどうしようもない、という諦めが、彼の思考を支配していた。まるで、分厚い壁の内側に閉じこもり、外の世界で何が起ころうと知覚しないように。そうやって、彼はかろうじて精神の均衡を保っていたのかもしれない。
その日も、健一はぼんやりと壁のシミを眺めていた。空腹を感じ、重い体を起こして玄関へ向かう。ドアを開け、冷たい外気に身を縮めながら、郵便受けを覗いた。いつも通り、広告や見慣れた差出人の封筒が数通。その中に、ひときわ異質な存在感を放つ、分厚く、硬質な紙の封筒があった。
差出人には、「東京地方裁判所」と、冷たく、厳格な明朝体で印字されている。
健一の心臓が、ドクン、と大きく跳ねた。裁判所?なぜ?一瞬、思考が停止する。何か悪いことでもしただろうか?いや、情報漏洩は会社との問題で、刑事事件にはなっていないはずだ。では、一体…?
嫌な予感が、背筋を冷たい汗となって伝う。震える指で、その封筒を掴み取った。他の郵便物は、どうでもよくなった。部屋に戻り、ドアを閉める。封筒の重みが、やけに現実的だった。
深呼吸を一つ。意を決して、封を切る。中から現れたのは、何枚もの書類の束だった。一番上の書類には、太いゴシック体でこう書かれていた。
『不動産競売開始決定』
その文字を目にした瞬間、健一の頭の中が真っ白になった。「けいばい…?」。言葉の意味は分かる。だが、それが自分の身に起こっていることだとは、到底信じられなかった。
書類をめくる。そこには、彼の名前、住所、そして、この家の所在地が正確に記載されていた。債権者として銀行の名前、保証会社の名前。そして、「差押命令」という、さらに追い打ちをかけるような言葉。
『…貴殿所有の下記不動産に対し、債権回収のため、強制競売の手続きを開始することを決定しました…』
冷たく、事務的な文章が続く。滞納額、遅延損害金、そして、この家が差し押さえられたという事実。
「うそだ…」
乾いた声が漏れた。書類を持つ手が、わなわなと震え出す。忘れていた。いや、忘れようとしていた。住宅ローンの存在を。毎月、確実に引き落とされていたはずの、あの重い負担を。自分が現実から目を背けている間に、水面下で、着々と、破滅への手続きが進んでいたのだ。
あのシミュレーションの言葉が、雷鳴のように頭の中で轟いた。
『家の差し押さえ: 住宅ローンの滞納が3ヶ月を超え、銀行は保証会社に代位弁済を請求。…家は差し押さえられ、競売にかけられることが決定する。裁判所からの通知がポストに投函される。』
寸分違わぬ現実。まるで、あのAIが書いた脚本通りに、自分の人生が進んでいるかのようだ。恐怖と、言いようのない無力感が、津波のように押し寄せてきた。
健一は、その場にへたり込んだ。書類が、手から滑り落ち、床に散らばる。彼は、ただ、荒れ果てた部屋を見回した。壁に貼られたままの、色褪せた息子の絵。キッチンに残る、妻が使っていたマグカップ。この、ささやかながらも家族の歴史が刻まれた場所が、もうすぐ、自分のものではなくなる。
「ああ…ああああ…」
声にならない嗚咽が、喉の奥から込み上げてきた。涙は出なかった。ただ、胸を締め付けるような激しい痛みと、底なしの絶望だけが、そこにあった。
裁判所からの通知。それは、健一にとって、社会からの最終的な死刑宣告にも等しい、「赤紙」だったのだ。
焼け跡に残る借金
競売の手続きは、健一の意思とは無関係に、冷徹に進んでいった。裁判所の執行官が家を訪れ、内部を調査し、評価額が算出された。その間、健一はただ、抜け殻のようにその様子を眺めていることしかできなかった。抵抗する気力も、権利を主張する知識も、彼には残されていなかった。
そして、運命の日が訪れた。競売の結果を知らせる通知が、再び無機質な封筒で届けられたのだ。前回と同じように、震える手で封を開ける。そこに記されていたのは、残酷な現実だった。
『落札価格:450万円』
健一は、その数字を何度も見返した。450万円?この家が?確かに築年数は経っている。しかし、駅からもそれなりに近く、家族3人で暮らすには十分な広さがあったはずだ。市場価格なら、少なくとも1000万円以上の価値はあったはずなのに…。競売というシステムが、買い手有利に働くことは知っていた。だが、これほどまでに低いとは。まるで、叩き売られるように、家族の思い出が詰まった場所が値付けされたのだ。
さらに、書類には追い打ちをかけるような計算が記されていた。
『ローン残高:980万円』
『落札価格:450万円』
『諸費用(競売費用等):約30万円』
『残債務額:560万円』
560万円。
その数字が、健一の目に焼き付いた。家を失った。それだけではない。家を失った上に、560万円もの借金だけが、まるで焼け跡のように、彼の人生に重くのしかかってきたのだ。
「…はは…」
乾いた笑いが漏れた。あまりの現実に、感情が追いつかない。絶望を通り越して、もはや滑稽さすら感じてしまう。全てを失い、さらにマイナスからのスタート。いや、スタートラインにすら立てていない。奈落の底に突き落とされ、さらに重りをつけられたようなものだ。
『自己破産も考えるが、弁護士費用が捻出できない。』
シミュレーションのこの一文が、再び脳裏をよぎる。そうだ、自己破産という手があるかもしれない。この莫大な借金から解放される唯一の方法かもしれない。
健一は、埃をかぶったノートパソコンを開き、震える指で「自己破産 弁護士費用」と検索した。画面には、数十万円という金額が表示された。同時廃止ならまだしも、管財事件になればさらに高額になる可能性もあるという。
数十万円…。
今の健一にとって、それは天文学的な数字だった。財布の中には、数千円の現金と、もう使えないクレジットカードだけ。銀行口座の残高は、ほぼゼロに近い。日々の食費すら、コンビニの安いパンやカップ麺でギリギリ賄っている状態だ。弁護士に相談に行く交通費すら、惜しいと感じるほど困窮している。
「無理だ…」
力なく呟き、パソコンを閉じた。自己破産という、最後の蜘蛛の糸すら、彼には掴むことができない。費用が捻出できないという、あまりにも現実的な壁が、彼の前に立ちはだかっていた。
家を失い、家族を失い、職を失い、そして今、借金だけが残った。未来への道は、完全に閉ざされたように感じられた。窓の外は、もうすっかり日が暮れて、冷たい闇が部屋を包み込んでいる。その闇は、まるで健一自身の未来を象徴しているかのようだった。
彼は、ただ、床に散らばった競売結果の通知を、虚ろな目で見つめ続けることしかできなかった。残されたのは、圧倒的な無力感と、これからどうすればいいのか全く分からない、深い深い絶望だけだった。
雨中の追放
競売の結果通知から数日が過ぎた。健一は、その間もほとんど何もできずにいた。部屋に積み上げられたままの、開封されない郵便物。散乱したゴミ。そして、日に日に色濃くなる絶望感。立ち退き期限が迫っていることは理解していたが、どこへ行けばいいのか、何をすればいいのか、全く見当がつかなかった。まるで、分厚い霧の中に置き去りにされたようだった。
その日は、朝から冷たい雨が降りしきっていた。窓ガラスを叩く雨音が、やけに大きく部屋に響く。健一は、薄汚れた毛布にくるまり、ただぼんやりと天井を眺めていた。空腹すら感じなくなっていた。
ピンポーン…
突然、けたたましくインターホンが鳴った。健一の心臓が、嫌な音を立てて跳ね上がる。また銀行か、あるいは保証会社か。無視しようかと思ったが、執拗に鳴り続けるチャイムに、彼は重い体を起こさざるを得なかった。
のろのろと玄関に向かい、ドアスコープを覗く。そこには、黒い傘を差し、冷たい表情をしたスーツ姿の男が立っていた。見覚えのない顔だ。
恐る恐るドアを少し開けると、男は名刺を差し出した。
「鈴木不動産の者です。先日この物件を落札された方の代理で参りました。本日が立ち退きの期限日ですが、ご準備はいかがでしょうか?」
事務的で、感情のこもらない声だった。健一は、言葉を失った。ああ、ついにこの日が来たのか、と。
「…まだ、荷物が…」
かろうじて、それだけを絞り出す。
男は、健一の背後、散らかった部屋の中を一瞥し、小さくため息をついた。
「困りますね。期限はとっくにお伝えしてあるはずです。これ以上、不法に占拠されるのでしたら、法的な手続きを取らざるを得なくなりますよ。強制執行となれば、あなたにとっても不利益しかありませんが?」
その言葉は、脅しというより、淡々とした事実の告知だった。健一には、それに抗う術も、気力もなかった。
「…分かりました。すぐに出ます」
力なくそう答えると、男は
「では、30分後にまた来ます。それまでに、必要なものだけまとめて外に出てください。残されたものは、残念ですがこちらで処分させていただきます」
と冷たく言い放ち、踵を返した。
30分。
健一は、呆然と部屋の中を見回した。どこから手をつければいいのか分からない。服、本、食器、家具…。かつては生活の証だったものたちが、今はただのガラクタの山にしか見えなかった。
彼は、クローゼットから一番大きなリュックサックを取り出した。そして、最低限の着替え、下着、洗面用具を詰め込む。通帳と印鑑、わずかな現金、そして、財布の中の色褪せた家族の写真。それだけが、彼がこの家から持ち出せる全てだった。
壁に貼られたままの、息子の描いた絵。妻が好きだった、欠けたマグカップ。本棚に並んだ、かつての愛読書。それらを一つ一つ手に取るたびに、胸が締め付けられるような痛みが走る。だが、リュックサックはもうパンパンだった。多くは、この場所に置いていくしかない。それは、過去との決別を強制される儀式のようだった。
時間だけが、無情に過ぎていく。
再びインターホンが鳴り、健一はリュックサックを背負い、玄関に向かった。ドアを開けると、先ほどの男が、相変わらず冷たい表情で立っていた。
「準備はできましたか?」
「…はい」
男は、健一が持っているのが小さなリュックサック一つだけなのを確認すると、無言でドアを開けたまま、外に出るよう促した。
健一は、最後にもう一度だけ、部屋の中を見回した。散らかった部屋の向こうに、家族と過ごした日々の幻影が見えた気がした。だが、それも一瞬のこと。彼は、深く頭を垂れ、雨が降りしきる外へと足を踏み出した。
「鍵は?」と男が問う。
健一は、ポケットから鍵を取り出し、男に手渡した。カチャン、と軽い金属音が響く。その音は、彼がこの家との繋がりを完全に断ち切られたことを告げていた。
男は、受け取った鍵で素早くドアを施錠し、「ご苦労様でした」とだけ言って、足早に去っていった。
健一は、雨の中に一人、取り残された。背中のリュックサックだけが、彼の全財産だ。見慣れたはずの家のドアは、もう固く閉ざされ、他人行儀な壁のように見えた。
雨は、勢いを増していた。冷たい雫が、容赦なく健一の体を濡らす。彼は、どこへ行く当てもなく、ただ、濡れたアスファルトの道を歩き始めた。
「路頭に迷う」
その言葉の意味を、彼は今、骨身にしみて理解していた。家を失い、文字通り、行くべき場所がない。空を見上げても、ただ灰色の雨雲が広がっているだけだった。足元には水たまりができ、彼の疲弊しきった姿を映し出していた。それは、絶望という名の、長い長い道のりの始まりだった。
雨中の漂流、安息なき夜
降りしきる午後の雨の中、健一はあてもなく歩いていた。背中のリュックサックが、鉛のように重い。数時間前まで自分の「家」だった場所は、もう冷たく閉ざされた壁の向こうだ。雨粒が容赦なく顔を打ち、濡れた前髪が視界を遮る。体は芯から冷え切っていたが、それ以上に心が凍てついていた。
ふと、彼は立ち止まり、濡れた手でズボンのポケットを探った。ごわごわとした感触の財布を取り出す。開くと、数枚の千円札と小銭、そして、隅に入れたままだった家族の写真があった。
雨に濡れないよう、手のひらで覆いながら、その色褪せた写真を見る。満面の笑みを浮かべる妻と、まだ幼い息子の顔。公園で撮った、何でもない日常の一コマ。あの頃は、こんな未来が来るなんて想像もしていなかった。幸せだったはずの過去が、今は鋭い刃となって胸を突き刺す。
「…すまない…本当に…すまない…」
声にならない嗚咽が漏れた。雨なのか涙なのか、頬を伝う雫の区別はつかない。なぜ、あんな過ちを犯してしまったのか。なぜ、もっと早く相談できなかったのか。後悔の念が、嵐のように心を打ちのめす。だが、いくら悔やんでも、失われた時間は戻らない。家族も、家も、仕事も、全て自分の手で壊してしまったのだ。
写真をそっと財布に戻し、健一は再び歩き出した。感傷に浸っている余裕はない。今夜、どこで眠るのか。それが、差し迫った現実だった。所持金は、財布の中のわずかな現金だけ。ホテルはもちろん、安宿に泊まる余裕すらない。
視界の先に、「ネットカフェ 24時間営業」の看板がぼんやりと見えた。煌々としたネオンが、雨に濡れたアスファルトに反射している。選択肢は、ほとんどなかった。
重い足取りで、そのビルの階段を上る。薄暗い店内には、独特の空気が漂っていた。タバコの匂い、芳香剤の甘ったるい香り、そして、どこか淀んだような閉塞感。受付で、一番安いナイトパックの料金を支払う。身分証の提示を求められ、免許証を出す手が微かに震えた。自分が社会の底辺に落ちていくような感覚があった。
案内されたのは、狭いリクライニングシートのブースだった。隣のブースからは、ゲームの音や、誰かの寝息が聞こえてくる。プライバシーなど、ほとんどないに等しい。健一は、濡れたリュックサックを足元に置き、深くため息をついた。
空腹を感じ、店内の自販機で一番安いカップ麺を買った。お湯を注ぎ、待つ間の3分間が、やけに長く感じられる。出来上がった麺を、無心ですする。味など、ほとんどしない。ただ、胃に何かを詰め込むだけの作業だった。
夜が更けても、健一はなかなか寝付けなかった。リクライニングシートは硬く、体中が痛む。周囲の物音や、モニターの明かりが気になって仕方がない。目を閉じれば、追い出された家の光景、妻子の顔、そして、これからどうなるのかという底知れない不安が押し寄せてくる。
数時間後、ようやく浅い眠りに落ちたが、すぐに悪夢で目が覚めた。汗びっしょりになり、心臓が激しく鼓動している。もう一度眠ろうとしても、神経は高ぶったままだった。
翌朝、健一は重い体を引きずってネットカフェを出た。シャワーを浴びる気力も、その料金を払う余裕もなかった。昨日と同じ、湿っぽい服のまま。顔には疲労の色が濃く、髭も伸び放題だ。
その日から、彼の「住居不定」の生活が始まった。
所持金は、日ごとに減っていく。ネットカフェの料金すら惜しくなり、夜は24時間営業のファミレスで、ドリンクバーだけを頼んで粘るようになった。店員の冷たい視線が痛い。時には、公園のベンチで仮眠をとることもあったが、寒さと不安で熟睡などできるはずもなかった。
食事は、コンビニの割引されたパンや、100円ショップのお菓子が中心になった。空腹を満たすことだけが目的で、栄養バランスなど考える余裕はない。
清潔さを保つことも、次第に困難になっていった。着替えはリュックサックの中にある数枚だけ。洗濯する場所も金もない。体からは汗と汚れの匂いが漂い始め、自分でも不快に感じるほどだった。鏡に映る自分の姿は、かつての面影を失い、やつれて薄汚れた、見知らぬ男のものになっていた。
社会との繋がりは、完全に断たれた。誰かに連絡を取る気力も、資格もないと思っていた。スマートフォンは、とっくに料金未払いで止められている。
彼は、都会の喧騒の中で、見えない壁に囲まれた孤独な漂流者となった。セーフティネットと呼ばれるものは、彼の手の届かないところにあった。あるいは、彼自身がその網の目から滑り落ちてしまったのかもしれない。
心身は、確実に蝕まれていた。絶望と疲労、栄養不足、そして、未来への希望の喪失。それは、緩やかでありながら、確実な破滅への道筋だった。雨の中、財布から家族の写真を取り出したあの午後の決意とは裏腹に、健一はただ、流されるままに沈んでいくしかなかった。
最後の扉、閉ざされた窓口
ネットカフェやファミレスを転々とする生活が数週間続いた頃、健一の体力と精神は限界に近づいていた。所持金は底をつきかけ、まともな食事はもう何日も口にしていない。体は常に重く、思考は鈍麻し、わずかな希望すら見いだせない暗闇の中にいた。
そんな彼が、最後の力を振り絞って向かった先があった。市区町村の役所、生活福祉課の窓口だ。生活保護――それが、今の彼に残された、文字通り最後の頼みの綱だった。
みすぼらしい、数日着たままの服。伸び放題の髭。虚ろな目。役所の清潔で明るいロビーは、今の健一にとって場違いな空間に感じられた。周囲の視線が突き刺さるようで、彼は俯きながら「生活福祉課」の案内表示を探した。
番号札を取り、待合の硬い椅子に腰を下ろす。心臓が早鐘のように打っていた。ここで断られたら、もう本当に終わりだ。そんな恐怖と、わずかな期待が入り混じる。
やがて番号が呼ばれ、健一は指定された相談ブースへと向かった。アクリル板越しに座る担当者は、淡々とした表情で彼を迎えた。
「ご相談内容は?」
「…生活に困窮しており…生活保護の申請を…お願いしたいのですが…」
か細い声で、健一は切り出した。
担当者は、手元の書類に目を落としながら、事務的な口調で質問を始めた。氏名、年齢、最終学歴、職歴…。健一は、途切れ途切れに答えていく。そして、最も答えにくい質問が来た。
「前の会社を辞められた理由は?」
「…懲戒…解雇です」
その言葉に、担当者の眉がわずかに動いた。ペンを走らせる音が、やけに大きく響く。
「解雇の理由は?」
「…情報…漏洩です…」
担当者は、顔を上げ、値踏みするような視線を健一に向けた。
「佐藤さん、まだ42歳ですよね? 十分働ける年齢だと思いますが、お仕事はお探しにならなかったのですか?」
「探しました…でも、懲戒解雇ということがネックになって…どこも…」
「ハローワークには行かれましたか? 求職活動の具体的な記録はありますか?」
健一は、数週間前の惨憺たる求職活動を思い出した。記録など、残していない。そもそも、短期バイトすら続かなかったのだ。
「…いえ、記録は…」
担当者は、ため息をついた。
「失礼ですが、仕事を探す努力が十分とは言えないのではないでしょうか。生活保護は、働く能力のある方が働く努力をせず、安易に頼るための制度ではありません」
その言葉は、正論でありながら、今の健一にはあまりにも冷たく響いた。努力する気力すら、もう残っていないのだ。
さらに、担当者は続けた。
「現在のお住まいは?」
「…家を失い…今は、ネットカフェなどを…」
「住所不定ということですね。うーん、そうなると申請手続きが難しくなります。まずは、安定した住居を確保することが先決かと…」
担当者は、生活保護申請に必要な書類のリストを健一の前に置いた。住民票、収入証明、資産証明、戸籍謄本、離職票、通帳のコピー…。リストは長く、今の健一には、それらを揃えること自体が途方もない作業に思えた。どこで、どうやって? 費用は? 気力は?
「これらの書類を揃えて、再度来ていただけますか? ただ、申請が受理されるかどうかは、調査の上での判断になります。特に、まだお若いですし、就労の意思と能力があると判断されれば、保護の対象とならない可能性も高いです」
その言葉は、事実上の「門前払い」に近かった。担当者の目には、同情の色はなく、ただ「厄介な相談者が来た」というような、うんざりした色が浮かんでいるように見えた。
健一は、もう何も言えなかった。わずかに残っていた希望の灯が、完全に吹き消された瞬間だった。書類のリストを手に取る気力もなく、彼は力なく立ち上がった。
「…分かりました…」
それだけ言うのが精一杯だった。ふらつく足取りで相談ブースを離れ、役所の出口へと向かう。背後で、担当者が次の番号を呼び出す声が聞こえた。自分は、この社会のセーフティネットから、完全に見捨てられたのだ。
外に出ると、午後の日差しがやけに眩しく感じられた。しかし、健一の世界は、より一層深い闇に閉ざされたようだった。申請に必要な書類を集める気力など、もうどこにもない。ただ、絶望的な無力感だけが、彼の全身を支配していた。
最後の扉は、固く閉ざされた。もう、頼れるものは何もない。彼は、ただ、当てもなく歩き出すしかなかった。心身の悪化は、もう誰にも止められない段階に入っていた。
蝕まれる心身、届かぬ救済
役所の冷たい対応に打ちのめされ、健一は再びあてのない放浪に戻った。もはや「生活を立て直す」という思考すら、彼の頭からは消え失せていた。ただ、瞬間瞬間の空腹と眠気、そして絶え間ない不安感に突き動かされるように、街を徘徊するだけの日々。
夜は、人目を避けて公園のベンチや、ビルの軒下で体を丸めた。昼間手に入れたコンビニの廃棄寸前のパンや、時には自販機の下に落ちている小銭で買った缶コーヒーが、唯一の栄養源となることもあった。シャワーなど何日も浴びておらず、体からは酸っぱい汗の匂いが漂い、服は薄汚れ、髪は脂でべたついている。かつての清潔好きだった自分が嘘のようだ。
しかし、肉体的な困窮以上に深刻だったのは、精神の蝕みだった。鏡を見ることもなくなり、自分の姿かたちへの関心は失せた。街行く人々の楽しそうな会話や笑顔が、まるで別世界の出来事のように感じられる。時折、ふと「もう、いっそ…」という暗い考えが頭をよぎるが、それを実行するだけの気力すら湧いてこない。ただ、感情のない人形のように、時間が過ぎるのを待っているだけだった。
持病だった軽い喘息の気配が、最近また顔を出し始めていた。だが、健康保険証は、とっくに有効期限が切れているのか、あるいは資格自体を失っているのか、定かではない。いずれにせよ、保険料など払えるはずもなく、病院のドアを叩くことなど夢のまた夢だった。診察料も薬代も、今の彼には天文学的な金額に思えた。
そんなある日の夕暮れ時。冷たい風が吹き抜ける、人通りの少ない高架下で雨宿りをしていた健一は、急に背筋に悪寒が走るのを感じた。体が鉛のように重く、頭がズキズキと痛む。明らかに、体調がおかしい。風邪でも引いたのだろうか。
その瞬間、抑えようもなく、激しい衝動がこみ上げてきた。
「ヘッ… ヘェーーックシュンッ!!!」
それは、ただのくしゃみではなかった。体の芯から絞り出すような、乾いた、それでいて不気味なほど大きな音だった。反動で体が大きく揺れ、壁に手をつかなければ倒れそうになる。くしゃみの衝撃で、一瞬、視界が白く霞んだ。
息を整えようとすると、再び強い悪寒が全身を駆け巡った。まるで、冷たい水の中に突き落とされたような感覚。喉の奥がヒリヒリと痛み、頭痛はさらに酷くなっている。自分の体が、もはや自分のコントロール下にはないことを、嫌でも思い知らされた。
(ああ…まずい…)
健一は、本能的に悟った。これは、ただの風邪ではないかもしれない。少なくとも、今の自分の体力では、このまま悪化すれば命に関わるかもしれない、と。
しかし、どうすればいい? 薬局で風邪薬を買う? 財布の中には、数十円の小銭しかない。病院に行く? 論外だ。誰かに助けを求める? 誰に? 家族は去り、友人の連絡先も知らない。親族には、合わせる顔がない。
彼は、NPO法人や炊き出しといった、困窮者を支援する団体の存在を知らなかった。社会から孤立し、情報からも遮断された彼にとって、そうしたセーフティネットは存在しないも同然だった。彼の知る世界には、もう助けを求める場所はどこにもなかったのだ。
再び、激しい咳がこみ上げてきた。ゴホッ、ゴホッ、と痰の絡んだ咳が止まらない。咳き込むたびに、胸が痛む。
健一は、冷たいコンクリートの壁に背中を預け、ずるずると座り込んだ。雨音と、自分の荒い息遣いだけが聞こえる。急速に失われていく体温と、じわじわと広がっていく体の痛み。そして、それら全てを包み込むような、深い、深い絶望感。
健康という、失って初めてその価値を知る最後の砦が、今、音を立てて崩れ落ちようとしていた。病院にも行けず、薬も買えず、ただ己の体の衰弱を待つしかない。それは、あまりにも残酷で、あまりにも孤独な現実だった。
陽光の下の残骸
数日前、高架下で激しい悪寒と咳に襲われた健一だったが、奇跡的に持ち直したのか、あるいは体が麻痺してしまったのか、今はただ鈍い倦怠感だけが残っていた。しかし、それは回復とは程遠い、生命力が枯渇していく過程の小康状態に過ぎなかった。
その日は、久しぶりに雲一つない、突き抜けるような青空が広がっていた。初夏の日差しが容赦なく降り注ぎ、公園の緑を鮮やかに照らし出している。子供たちの楽しそうな声、ベンチで談笑する老人たち、散歩を楽しむ人々。平和で、ありふれた日常の風景。
その公園の隅にある、古びたベンチに、健一は亡霊のように座っていた。
数日前の雨で濡れた服は乾いたものの、泥や埃で汚れ、異臭を放っている。最後に髭を剃ったのはいつだったか、もはや思い出せない。伸び放題の無精髭は顔の半分を覆い隠し、目の下の隈は深く、頬はこけていた。虚ろな目は、公園の明るい風景のどこにも焦点を結んでいない。
時折、近くを通りかかる人が、訝しげな、あるいは嫌悪感を隠さない視線を彼に向ける。母親は子供の手を引き、足早に通り過ぎていく。健一は、もはやそうした視線に傷つくことすらなくなっていた。自分が社会にとって「異物」であり、「避けられるべき存在」であることを、何の感情もなく受け入れていた。
ポケットを探ると、昨日、なけなしの小銭で買った安価なワンカップ酒の容器が手に触れた。彼はそれをゆっくりと取り出し、蓋を開ける。ツンとしたアルコールの匂いが鼻をついたが、それに対する嫌悪感も、渇望もなかった。ただ、習慣のように、それを呷る。
喉を焼くような感覚。しかし、味はほとんど感じない。酔いが回る感覚も、以前ほどはっきりとはしなかった。ただ、わずかに意識がぼんやりとし、現実の重みが少しだけ薄れるような気がするだけだ。それが、今の彼にとって唯一の慰めだった。
(これから、どうする…?)
そんな問いが、一瞬だけ頭をよぎる。しかし、すぐに霧散してしまう。考える気力が、もうないのだ。再就職? 住む場所? 借金? 家族? それらは全て、あまりにも遠い、手の届かない世界の言葉のように思えた。
かつては、仕事で複雑なプロジェクトを管理し、部下を指導し、家族との将来設計を語り合っていた自分がいた。その記憶すら、まるで他人の人生のフィルムを見ているかのように、現実味がない。
思考は断片的で、まとまりがない。ただ、目の前の陽光の眩しさ、子供たちの甲高い声、遠くを走る車の音、そして自分の内側から湧き上がる、底なしの虚無感だけが、ぼんやりとした現実だった。
もう、何もかもどうでもいい。
頑張る気力も、後悔する気力も、悲しむ気力すら、枯渇してしまった。
ただ、このまま時間が過ぎて、いつか全てが終わればいい。
健一は、再びワンカップ酒を呷った。空になった容器を、力なくベンチの脇に置く。
晴れ渡った空の下、彼はただ、生きる屍のように座っていた。精神は完全に荒廃し、自ら状況を打開しようという意志は、ひとかけらも残っていなかった。
陽光は、彼の汚れた姿と、その周囲に漂う絶望の影を、皮肉なほどくっきりと映し出していた。社会との繋がりは完全に断たれ、彼は緩やかに、しかし確実に、終わりへと向かっていた。
都市の片隅、消えゆく灯火
季節は移ろい、街には冷たい木枯らしが吹きすさぶようになっていた。かつて佐藤健一が闊歩していたオフィス街のネオンサインは、今は遠い世界の光のように感じられる。彼の「住処」は、もはやネットカフェですらなかった。なけなしの小銭も尽き、彼に残されたのは、薄汚れた衣服と、衰弱しきった体だけだった。
夜は、人目を避けて、古びた神社の境内や、高架下の吹きさらしの空間で過ごした。段ボールを敷くことすら贅沢で、冷たいコンクリートの上に直接体を横たえる。凍えるような寒さが骨身に沁み、浅い眠りと覚醒を繰り返す。空腹はもはや常態となり、胃が痛む感覚すら麻痺していた。時折、ゴミ箱を漁って食べ物を探すが、それすら満足に見つけられない日も多い。
数週間前、激しく咳き込んだ日から、彼の体調は回復することなく、むしろ着実に悪化の一途をたどっていた。咳は止まらず、時折、血の混じった痰が出た。呼吸をするたびに、ゼイゼイと嫌な音が喉から漏れる。おそらく肺炎か、あるいは持病の喘息が致命的なレベルまで悪化しているのだろう。しかし、それを確かめる術も、治療する術も、彼にはなかった。
社会との繋がりは、完全に断たれていた。スマートフォンはとうの昔にただの文鎮と化し、誰かに連絡を取る手段も、誰かから連絡が来ることもない。道行く人々は、彼の存在に気づかないかのように通り過ぎていく。あるいは、汚物でも見るかのような視線を投げかけ、足早に去っていく。彼は、都市という巨大なシステムの中で、完全に忘れ去られた存在となっていた。生きているのか死んでいるのかすら、誰の関心事でもない。
ある凍てつくような冬の夜。
健一は、高架下の、風が少しだけ避けられる隅にうずくまっていた。薄いジャンパーだけでは、突き刺すような寒さを防ぐことはできない。体は芯から冷え切り、小刻みに震えが止まらない。
激しい咳が、再び彼を襲った。ゴホッ、ゴホッ…!咳き込むたびに、胸に激痛が走る。息が苦しい。酸素が足りない。まるで水の中にいるかのように、もがきながら浅い呼吸を繰り返す。
意識が朦朧としてきた。
目の前に、幻影がちらつく。
暖かいリビングで笑う妻と息子の顔。
会社のデスクでパソコンに向かう自分の姿。
情報漏洩が発覚した日の、人事部長の冷たい視線。
雨の中、家を追い出された日の、背中に感じた重いリュックの感触。
断片的な記憶が、走馬灯のように駆け巡る。
後悔? 悲しみ? 怒り?
もはや、そうした明確な感情は湧いてこなかった。ただ、ひたすらに寒く、苦しく、そして、どうしようもなく孤独だった。
(ああ…寒い…)
それが、彼が最後に抱いた明確な思考だったかもしれない。
体の震えが、次第に弱まっていく。
激しかった咳も、いつしか止んでいた。
呼吸は浅く、不規則になり、やがて、それも途絶えた。
まるで、凍てついた街の風景に溶け込むように、彼の体は動かなくなった。
高架下を吹き抜ける風の音と、遠くで響く車の走行音だけが、彼の最期を静かに見守っていた。
***
翌朝、通勤途中のサラリーマンが、高架下の隅で不自然な格好で動かなくなっている人影に気づいた。訝しげに近づき、声をかけるが反応はない。明らかに様子がおかしいことに気づき、彼は警察に通報した。
駆けつけた警察官と救急隊員によって、彼の死亡が確認された。
所持品はほとんどなく、身元を特定できるようなものは、汚れた財布に入っていた数枚の硬貨と、期限の切れたポイントカードくらいだった。
「身元不明、行旅死亡人として処理するしかないか…」
警察官の一人が、そう呟いた。
かつて佐藤健一という名前を持ち、家族と職を持ち、ささやかながらも未来を夢見ていた男は、こうして、誰にも知られることなく、都市の片隅で冷たい骸となった。彼の存在は、まるで初めからなかったかのように、雑踏の中に静かに消えていった。
目撃者の朝 – 日常の中の残響
健一が冷たくなった翌朝。
日曜日の柔らかな日差しが、高架下のコンクリート壁をまだらに照らしていた。昨日の騒ぎは嘘のように静まり返り、警察の姿も、規制線もない。ただ、清掃されたのか、一部だけ不自然に濡れた地面と、どことなく重苦しい空気が残っているだけだった。
そこへ、手をつないだ家族連れが通りかかった。父親は少し眠そうな顔で欠伸をし、母親は隣を歩く小さな息子の手をしっかりと握っている。公園へ向かう途中なのだろう、息子はカラフルなボールを抱えていた。
「パパ、見て! あそこ、昨日パトカーいっぱいいたとこだよね?」
息子が、高架下の隅を指さして言った。子供の目は、大人が見過ごしてしまうような些細な変化にも敏感だ。
父親は一瞬、顔をしかめた。昨夜、帰宅途中に遠巻きに見た光景を思い出したのだ。救急車とパトカーの赤いランプ、集まる野次馬、そして、担架で運ばれていく何か。
「ああ、そうだったかな…」
父親は曖昧に答える。
「誰かいたの? 悪い人?」
息子は純粋な好奇心で尋ねる。
母親が困ったように眉を寄せた。
「ううん、そうじゃないのよ、ケンちゃん。きっと、具合が悪くなっちゃった人がいたのね」
「ふーん…」
息子はまだ納得がいかない様子で、高架下の隅をじっと見つめている。
「でも、なんか、昨日と違う匂いがする…」
父親は息子の肩を軽く叩いた。
「気のせいだよ。さ、早く公園行こうぜ。新しい滑り台、楽しみだろ?」
「うん!」
息子の関心はすぐに公園へと移り、抱えたボールをポンポンと弾ませながら歩き出した。
子供が少し先に行ったのを見計らって、母親が小さな声で夫に囁いた。
「…かわいそうに。あんなところで、一人で…」
その声には、やるせない響きがあった。昨夜のニュースで、身元不明の男性が亡くなったことを知っていたのかもしれない。
父親は、無言で頷いた。自分も、いつどうなるか分からない。会社でのプレッシャー、住宅ローン、家族を養う責任。一つ歯車が狂えば、自分だって…そんな考えが、一瞬頭をよぎる。だが、すぐにそれを振り払った。
「…まあ、俺たちには関係ないことだ。さ、行こう」
彼は妻の背中を軽く押し、息子の後を追った。
家族は、何事もなかったかのように、明るい日差しの中を公園へと向かっていく。
高架下の隅に残された、見えない死の残響。
それは、都市の喧騒と、家族の暖かな日常の中に、あっけなくかき消されていった。健一の孤独な死は、誰かの記憶にわずかな染みを残しただけで、また一つ、名前のない物語として忘れ去られようとしていた。
エピローグ:都市の片隅、忘れられた警告
季節は巡り、凍てつくような冬は過ぎ去り、街には再び柔らかな春の日差しが降り注いでいた。佐藤健一が息絶えた高架下の隅にも、コンクリートの隙間から逞しく顔を出した名も知らぬ雑草が、小さな黄色い花を咲かせている。行き交う人々は、そのささやかな生命力に目を留めることもなく、それぞれの目的地へと足早に通り過ぎていく。あの場所でかつて、一人の男が孤独な死を迎えたことなど、誰も覚えてはいない。
彼がかつて情熱を注ぎ、そして裏切る形となった会社では、新しいプロジェクトがいくつも立ち上がり、社員たちは日々の業務に追われていた。情報漏洩事件は過去の出来事となり、セキュリティ対策は強化されたものの、その教訓がどれほど深く根付いているかは定かではない。時折、古い社員の間で「あの佐藤って人、いたよな」と噂話の断片が交わされることはあっても、彼の顔や人となりを鮮明に覚えている者は、もうほとんどいなかった。彼のデスクがあった場所には、新しい社員が座り、新しいファイルが積み重ねられている。
別れた妻と息子は、新しい街で静かに暮らしていた。母親は懸命に働き、息子を育てている。幼かった息子にとって、父親の記憶はすでに曖昧なものとなりつつあった。時折、母親がふと遠い目をして何かを思い出しているような表情を見せることはあっても、その理由を息子が知ることはない。彼らの生活は、健一という存在が欠けた場所で、それでも着実に前に進んでいた。
健一は、最終的に「行旅死亡人」として処理された。わずかな遺留品からは身元を特定するに至らず、引き取り手も現れなかった。彼の人生の記録は、役所の書類の片隅に記された無機質な文字列となり、やがてそれも、膨大な記録の海の中に埋もれていくだろう。彼が生きた証は、まるで陽炎のように、この世界から静かに消え去った。
都市は今日も変わらず動き続けている。高層ビルの窓には新しい一日が映し出され、人々はそれぞれの希望や不安を抱えて生きている。誰もが、自分は大丈夫だと信じている。自分だけは、あんな風にはならないと。
しかし、佐藤健一の転落は、決して遠い世界の出来事ではなかったのかもしれない。ほんの少しの油断、一つの過ち、そして、社会の網の目からこぼれ落ちた時に手を差し伸べてくれる存在の不在。それらが不幸な連鎖を起こした時、誰の足元にも、奈落へと続く見えない亀裂が口を開けているのかもしれない。
高架下を吹き抜ける春の風は、あの冬の夜の出来事を何も語らない。ただ、コンクリートの隙間に咲いた小さな黄色い花だけが、忘れられた男の物語を、誰に知られることもなく、静かに揺らしている。それは、この巨大な都市の片隅で繰り返されるかもしれない、声なき警告のようにも見えた。
(完)
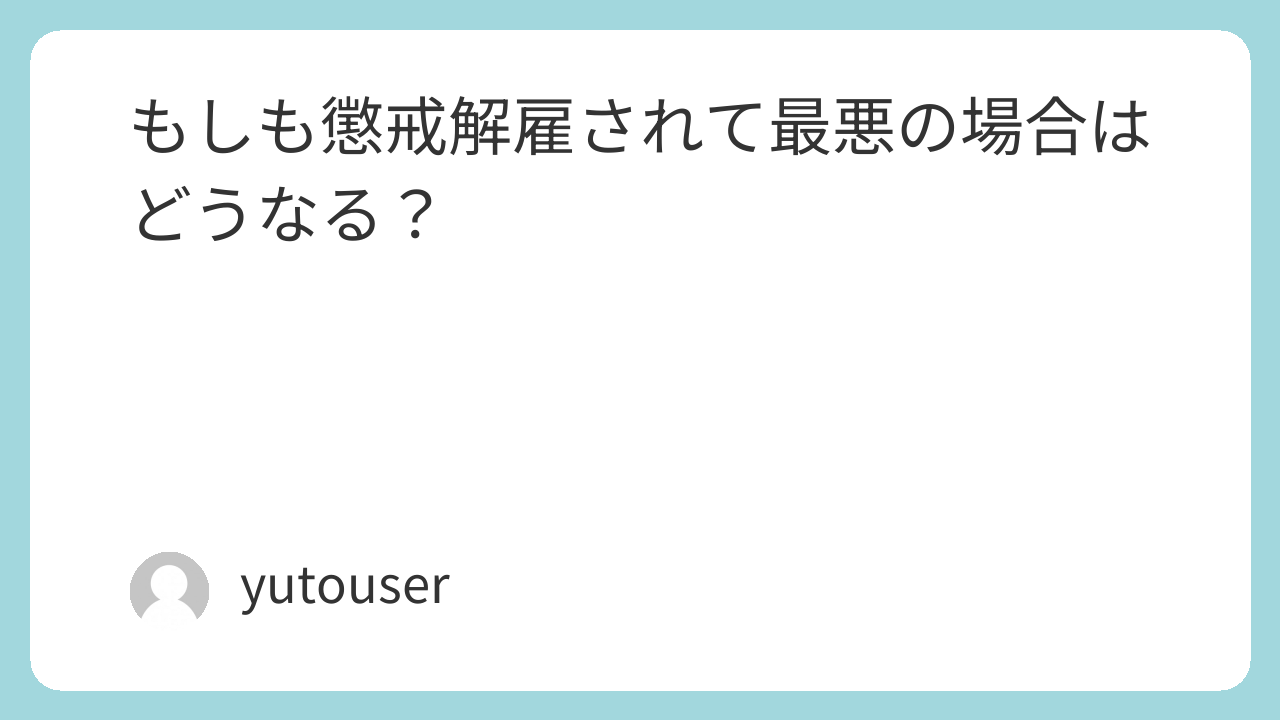
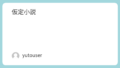

コメント